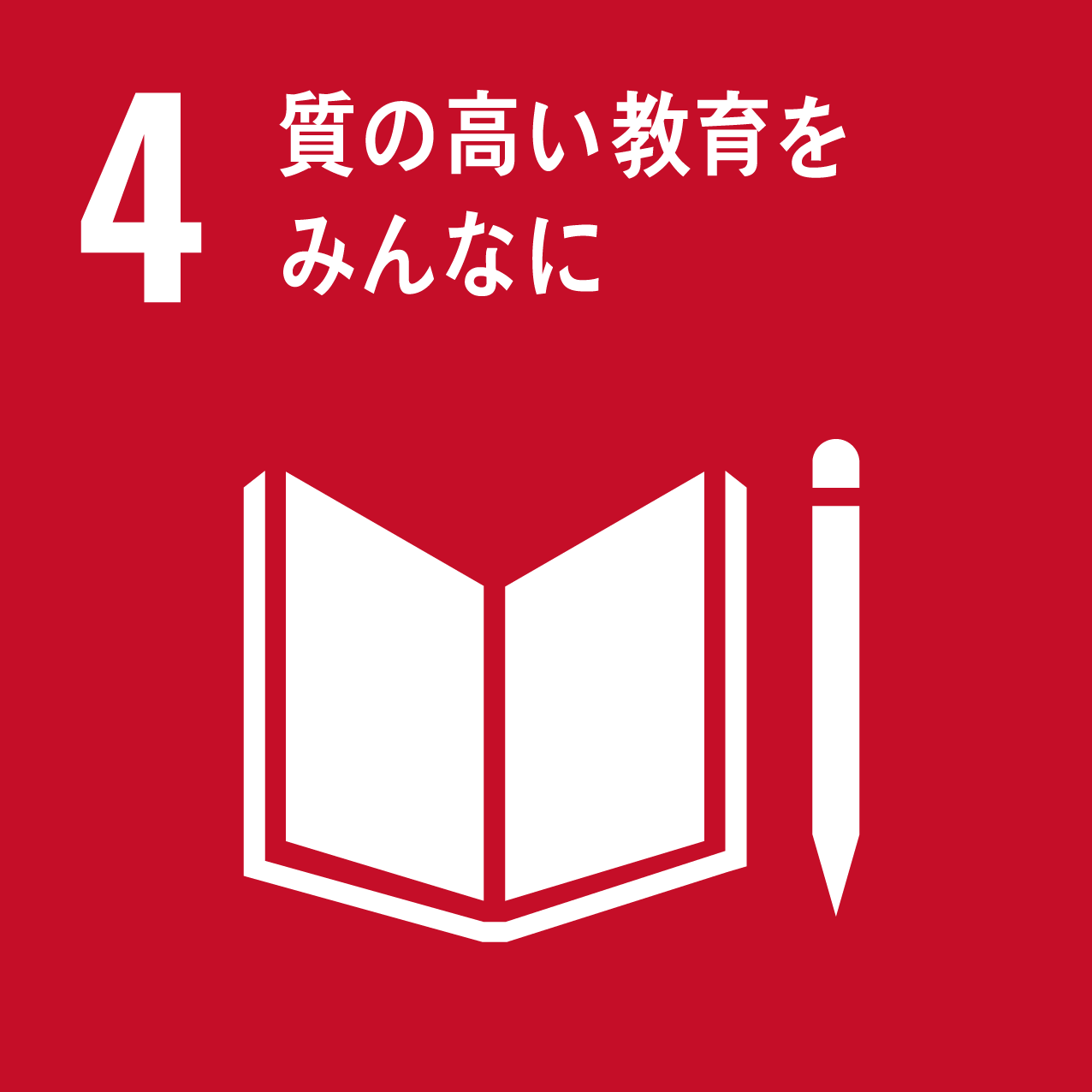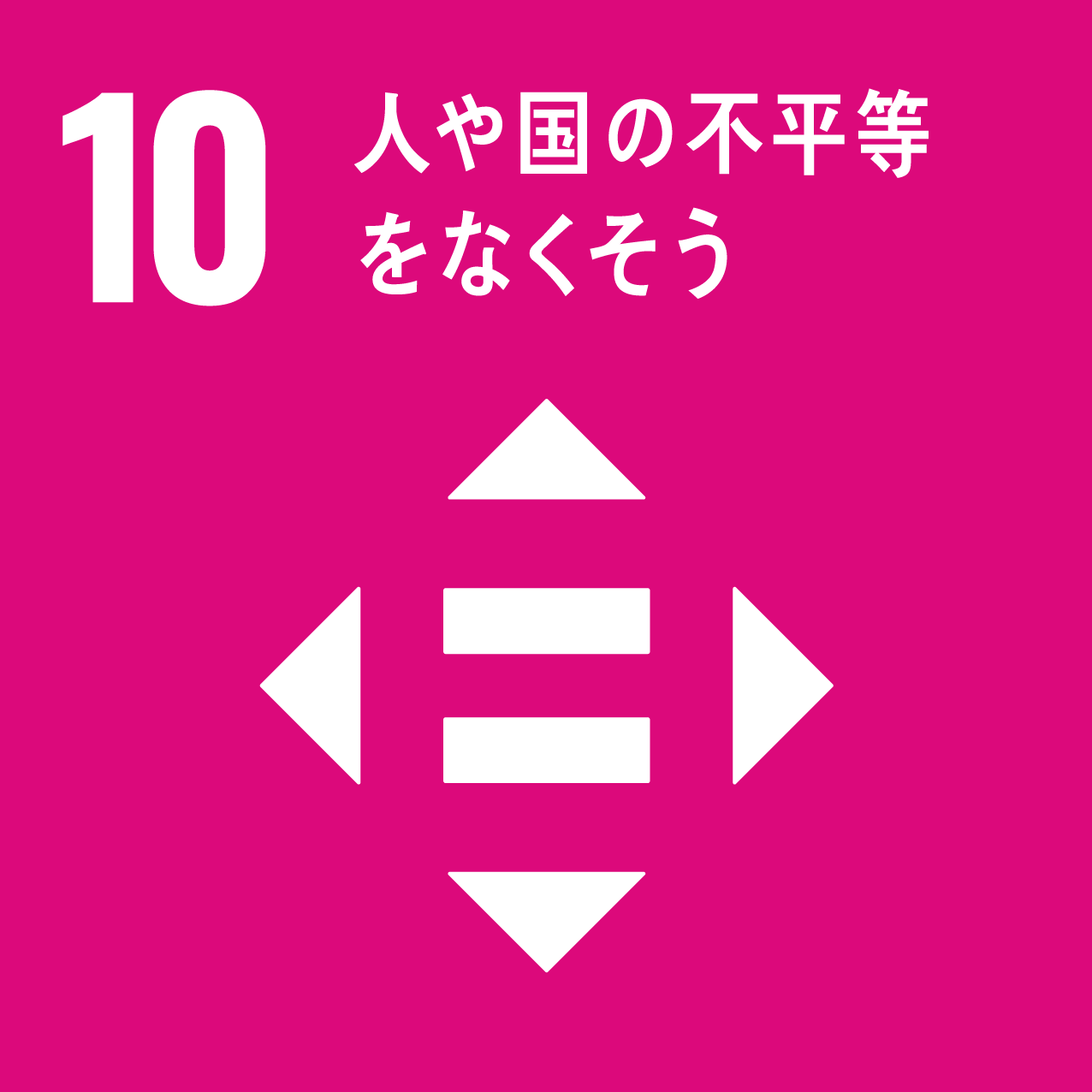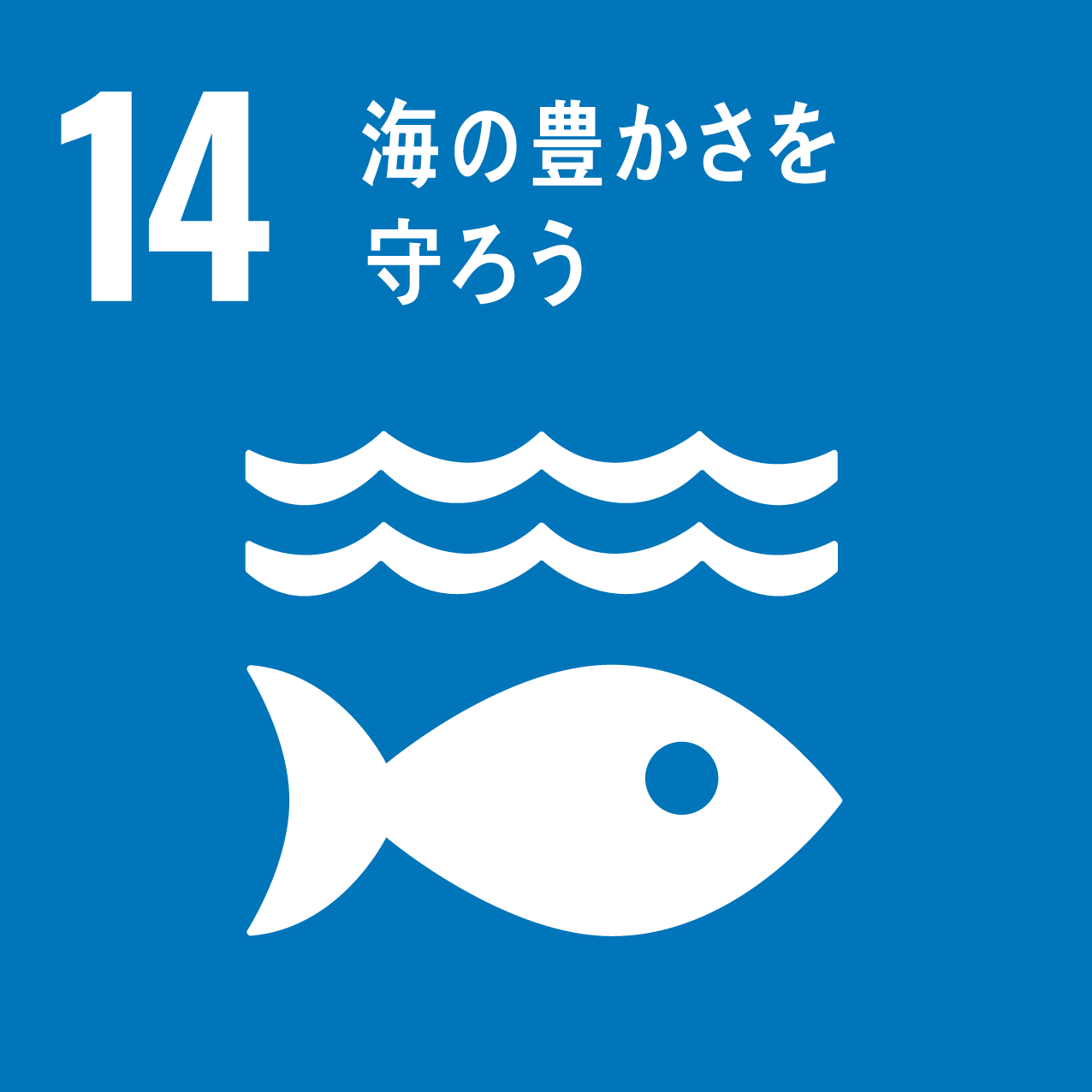若者が安心して過ごすことができて、夢や悩みを共有できる場所と機会を提供したい。そんな思いで20年11月に開設されたのは、長野県岡谷市にある「子ども・若者STEPハウス みんなの古民家」(以下「みんなの古民家」)です。立ち上げたのは、20年度緊急支援枠〈資金分配団体:公益財団法人長野県みらい基金〉の実行団体NPO法人子どもサポートチームすわ。同法人の理事長 小池みはるさんは、不登校の子どもたちを支援するフリースクールの活動を20年以上続けています。フリースクールを卒業した後に引きこもりに戻っていく子どもたちの現状を知り、「次の居場所が必要だ」と考えて、みんなの古民家を開設しました。みんなの古民家を続ける思いなどについてお聞きしました。
フリースクールを卒業した後の居場所づくり
みんなの古民家を運営するNPO法人子どもサポートチームすわは、岡谷市の隣にある諏訪市で、1997年からフリースクールを運営してきました。

20年以上にわたり、不登校の子どもたちが自分のペースで学べるよう支援を続けるなかで、巣立っていく子どもたちの“その後”に課題を感じていたと理事長の小池みはるさんは言います。

「フリースクールを卒業した後に家で引きこもりになったり、就職しても続かなかったりする子どもたちをたくさん見てきました。フリースクールに通っている期間は私たちがサポートできますが、本当に『引きこもり』になってしまうのは、その後なんですよね」

フリースクールを卒業した後も、子どもたちが安心して過ごせる居場所をつくりたい。その必要性を強く感じた小池さんは、新たな拠点の立ち上げを検討。場所を探していた小池さんに、ある出会いが訪れます。
「私が拠点をつくろうとしている話を聞いた方から、『古民家使う?』と電話をいただいたんです。とはいえ岡谷と諏訪は離れているし、連絡をいただいた当初は消極的でした。でも試しに子どもたちと一緒に見に来たら、一目で気に入ったんです。それが、この物件でした」
子どもから大人まで、誰もが集える「居場所」

「みんなの古民家」があるのは、岡谷駅から車で10分ほどの住宅地。敷地内には、築150年ほどの母屋、蔵と納戸があります。
2020年8月、次なる居場所をこの古民家に決めた小池さんは、活動の資金源として休眠預金の活用を申請し、古民家の改装を進めました。そして現在は、不登校の子どもたちや引きこもりの若者たちが安心して過ごせる居場所として、週に4日間開放。現在、定期的に通って来るのは小学生が2人。他にも中学生や高校生が訪れます。
場所を構えてみて、さまざまな事情を抱えた子どもや大人がいることを実感したと言います。
「例えば、専門学校を卒業した後に引きこもりになった27歳の男性が、ここに来るようになりました。彼は調理師の免許を持っていて、今ではここのスタッフとして週2回食事をつくってくれています。なぜみんなの古民家に通うようになったのかを聞いてみると、『人と普通に話せるのが良かった』と言うんです。他にも、『友だちが欲しかったから来た』と答える子がとても多くいます。
場を開くまでは、居場所をつくるだけでなくもっと具体的な支援を検討していたので、場を開いてみて初めて、彼らが一番求めていたことに気づかされました」

みんなの古民家では、子どもたちに向けたイベントや勉強会だけでなく、保護者向けの座談会も定期的に開催し、包括的なサポートの場になっています。
ある時は、引きこもって10年が経つ40歳の子どもがいる親御さんから、小池さんのもとに相談の電話がかかってきました。
「親御さんと私たちがつながっていれば相談を受けられますが、子どもが30代や40代にもなってくるとご家族が疲れてしまって、途中で連絡がなくなることも少なくありません。だからこそ『みんなの古民家』は、同じ経験をしている親御さんどうしが気持ちを分かち合える場所にしていきたいですし、年齢や事情に関わらず誰でも居場所にしてもらえたらと思います」
助けられる存在から、助ける存在へ
みんなの古民家を立ち上げてから、2023年で3周年。子どもたちが集まり、会話が生まれるなかで、助け合いの場面がたくさん見られています。
「みんなの古民家には個室がなくて、隠し事ができない空間です。誰かがポツリと悩みを話すと、『僕もそうだったよ』『焦らないでいいよ』と子どもたちが思いつくまま話している光景をよく目にします。引きこもっていた経験を誰かに話すことで、誰かの役に立てる。子どもたちは決して『支援を受けるだけ』の存在ではないことを実感しています」
さらに、かつて支援を受けていた子どもたちが、みんなの古民家で誰かをサポートする仕事に就くケースも生まれています。
「フリースクールを卒業して、今は古民家のスタッフとして働いてくれている人もいます。彼らの残りたい気持ちと、他に就職できるところがなかった現実の結果ですが、だんだんと循環が生まれてきました。
現在は、みんなの古民家の運営はほとんどスタッフに任せていて、私はなるべく入らないようにしています。スタッフの間で『ここに来る人に大切なのは、友だち・お腹を満たすこと・お金の使い方を学ぶことの3つ』といった話をしているようですね。毎月のイベント企画も、スタッフが考えています」

立ち上げ前から地域の方を中心にさまざまな方がサポートに加わってくれたそうで、場を開いた後もその関わりは続いています。
「地域と関わるなかで、区長さんが『引きこもっている子どもたちが地区に何人もいるのはわかってはいるけど、家庭のことだから、これまで口を出せなくて……』とおっしゃっていたのが印象に残っています」
みんなの古民家ができたことで地域に生まれた、新たなつながり。今では近隣の住民から、引っ越しや草むしりの手伝い、高齢者の買い物支援など、単発の仕事が入ることもあるそう。みんなの古民家から、地域のつながりが広がっています。

小池さんは、みんなの古民家に通う人たちが、もっと自分で稼ぐことのできる事業をつくりたいと考えています。
「例えば農園に行っても、収穫して売るだけの“いいとこどり”だけでなく、事業の一通りを自分たちの手でできるようにすることで、責任と社会性を持つ経験を提供したいと思っています」
近々、生活クラブとの協働でパン屋を始める計画があるそう。さらに、敷地内の蔵を使って何か新しいことができるように、小池さんの私費を使って改装しました。
「この古民家は、あくまでも走り出すための場所です。ここで準備をして社会へと走り出せるように、市の支援を活用したり自分で探せるようにサポートしたりと、自立のために背中を押していきたいです」

支援を継続するための3年目の課題
一方で、みんなの古民家3年目に向かって、運営の課題も見えてきました。
大きな悩みは資金面。休眠預金の事業年度が終了し、その他の助成金活用をはじめ、資金確保の方法を模索しています。
「どんな法人格にするのがいいのか、お金をどうしていくか、毎日悩んでいます。いただいた助成金や寄付を使っていくだけではなく、資金を増やしていく仕組みを考えなくてはいけないですね」
もう一つ、早急に必要なのは、引きこもっている子どもや若者たちに直接アクセスする広報活動です。現在はスタッフや子どもたちがSNSで発信しながら、公民館活動が盛んな岡谷の土地柄を活かしてチラシを置いてもらうなどの連携を進めています。
「これまではチラシやウェブサイトで広報してきましたが、それらにアクセスするのはほとんどが親御さんです。引きこもっている当事者と親御さんとの関係性が良好でない場合も多いですから、親御さんだけでなく『みんなの古民家』を求めている当事者に情報を伝えられるように、方法や手段を変えていかなくてはと考えています」

小池さんと子どもたちは、資金の目処がつけば、みんなの古民家で「文化祭」がしたいと話しているそうです。「引きこもりの人もそうでない人も、障がいのある人もない人も、誰でも来てほしい」と小池さんは話します。
「今の社会では、誰が引きこもりになってもおかしくありません。ですから誰もが引きこもりへの理解を深められる機会をつくったり、引きこもっている子どもたちのエネルギーをいかに引き出せるかを考えたりしていきたいですね。
生きるという点ではみんな同じ。場があれば助けることができるし、私たちや皆さんが助けられることもあるでしょうから、これからもみんなの古民家を続けていきたいです」
取材後、子ども・若者STEPハウスは、 NPO法人子どもサポートチームすわから独立。また、現在、公益財団法人長野県みらい基金が運営するサイトで、クラウドファンディングを実施中です。
【事業基礎情報】
| 実行団体 | 特定非営利活動法人子どもサポートチームすわ |
| 事業名 | コロナ禍の発達特性のある子ども・若者支援 |
| 活動対象地域 | 長野県諏訪市、岡谷市周辺地域 |
| 資金分配団体 | 長野県みらい基金 |
採択助成事業 | 2020年度コロナ枠 |
今回の活動スナップは、浦和レッドダイヤモンズ株式会社(資金分配団体:一般社団法人RCF)が11月20日に実施した〈このゆびとまれっず!ハートフルケア〉イベントにJANPIAスタッフが参加した際の様子をお伝えします。
活動の概要
浦和レッドダイヤモンズ株式会社は、一般社団法人RCF(20年度緊急支援枠資金分配団体)の実行団体として、「スポーツクラブによる困窮世帯支援事業」に取り組んでいます。
「このゆびとまれっず」は、地域の課題解決を目指し、クラブがきっかけとなって(=浦和レッズが指を掲げて)、支援者・賛同者とともに(=仲間を募って)、継続・拡大していくことを目的とし、
休眠預金活用事業をきっかけに立ち上がったアクションプログラムです。
さいたま市内の子ども食堂を利用している子どもたちへの支援策として、
心と体をケアするスポーツプログラム「ハートフルケア」、
食料・飲料・文具などの物的支援を行う「REDS Santa」、
本活動を広く発信することで支援の輪を広げる「このゆびとまれっず!特設サイト」の
3つの柱で構成されています。
活動スナップ
2021年11月20日、〈このゆびとまれっず!ハートフルケア〉が実施されました。
当日はさいたま市の子ども食堂を利用している親子69組146名が参加しました。




※アンプティサッカーとは 主に上肢、下肢の切断障害を持った選手がプレーするサッカー。義足・義手を外し、日常の生活やリハビリ医療目的で使用しているクラッチ(杖)で体を支えて競技を行います。 |



| 実行団体 | 浦和レッドダイヤモンズ株式会社 |
| 事業名 | このゆびとまれっず! |
| 活動対象地域 | 埼玉県 |
| 資金分配団体 | 一般社団法人RCF |
| 採択助成事業 | スポーツクラブによる困窮世帯支援事業〈2020年度緊急支援枠〉 |
https://youtu.be/WS89S3IVjuI
https://youtu.be/FyeSC12K8lA
「ダブルハルカヌーって安全性が高いんですよ」。そう爽やかな笑顔で話してくださったのは、有限会社SHIPMANの代表取締役を務める城田守さん。2019年度通常枠〈資金分配団体:公益財団法人 ブルーシー・アンド・グリーンランド財団〉の実行団体として、活動拠点である静岡県立三ヶ日青年の家(以下、青年の家)を舞台に浜名湖畔で体験格差をなくすべく、水辺の活動やさまざまな支援に取り組んでいます。今回は、日本でここにしかない「ダブルハルカヌー」に特別支援学校の子どもたちが挑戦!その体験学習の様子、そして休眠預金を活用したSHIPMANの取り組みなどを取材しました。
ダブルハルカヌーに挑戦。美しい浜名湖をみんなで駆け抜けよう
11月初旬、浜松市内の特別支援学校の生徒たちが三ヶ日青年の家を訪れていました。集まっていたのは、小学4年生と5年生の男女8名。聴覚障害を持つ児童たちです。彼らが今日体験するのは「ダブルハルカヌー」。浜名湖畔で、日頃、触れ合う機会のない水辺での体験学習に挑みます。

体育着姿の子どもたちが集まったのは、マリーナ広場にある艇庫(ボート倉庫)。その一角で、まずは水辺での活動の際に注意すべきことや漕ぎ方などについて学びます。大きなポイントは3つ。1つ目はSHIPMANの指導員や先生たちの話をよく聞くこと。2つ目はできる限り大きな声を出す。そして3つ目は素早い行動を心掛けること。水上ではちょっとした甘えが事故に繋がるため、一緒に乗船する艇長の指示に従って行動しなくてはなりません。続いて、水辺の活動では着用が欠かせないライフジャケットについて指導を受けます。
「ライフジャケットは必ず体が浮くようにできています。もし水の中に落ちてしまったら、体育座りのようにできるだけ小さな姿勢を保って救助を待ちます。落ち着いて襟元をしっかり掴んで下にぐっと引っ張りながら上を向いて呼吸を確保してください。暴れたり、泳いだりすると体力を消耗するので、静かに救助を待つよう注意しましょう」

着用したライフジャケットを触ってみたり、友だちと話してみたり、緊張した表情を浮かべつつも、どこか楽しげな様子の子どもたち。次は艇長の指導でパドルの持ち方や漕ぎ方を学びます。元気な挨拶が艇庫いっぱいに広がると、木製パドルが順番に配られました。いろいろ試してみたいところですが、ここはぐっと我慢!
「今、みんなに配ったのが、カヌーを漕ぐときに使用するパドルです。大事な道具なので杖にしたり、振り回したりしてパドルを傷つけたり、周りのお友だちに怪我をさせないように注意しましょう!」
艇長の両脇で引率の先生が手話で説明をします。口の動きと手話で持ち方を学ぶと、子どもたちは素早く行動。ダブルハルカヌーは二層のカヌーが並行に繋がれた仕様のため、乗船する場所によってパドルの持ち方が異なります。向かって右側の列は左手で上部の三角部分を握り、右手で一番細い部分を持ちます。左側の列は、その逆です。しっかり持つことができたら、いよいよ漕ぎ方の練習。友だちにぶつからないように距離を保ちます。
「漕ぐ時は “1、2、ソーレ!” という掛け声に合わせてパドルを動かします。艇長が1、2、みんなはソーレ!です。パドルを戻す時は後ろの人に水がかからないように、水からスッと抜くようなイメージ。ちょっとみんなで練習してみましょう!」

少し照れくさそうにしていた子もいつの間にかどんどん大きな声に。テンポ良くパドルを動かしながらイメージを膨らませます。しっかり準備ができたら、ここで持参した小さなタッパーに補聴器や人工内耳をしまいます。子どもたちは水辺での活動やプール学習の際はもちろん、雨の日も傘がない時は必ず装具を外すといいます。聞こえにくく不安に感じる際は周囲の状況をよく見ることに意識を向けるなど、日頃の自立活動の時間を通じて学んでいます。

水上で学ぶ「思いやり」と「協力」の姿勢
艇長に続いて艇庫を出ると、雄大な浜名湖が子どもたちを待っていました。ヨットハーバーに到着すると休眠預金を活用して購入したという真新しい桟橋から、指示に従ってダブルハルカヌーに乗船していきます。
浜名湖は海とは異なり、時折、すれ違う漁船による引き波以外は、大きな波もなく水面は穏やか。これまでに経験のない揺れに驚いて声を出す子もいましたが、ぐんぐん進むうちにいつの間にか掛け声も大きく、パドルも力強く揃った動きに。前にいる仲間の動きをよく見て、後ろの友だちのことを思いやり、協力して漕いだダブルハルカヌー。ヨットハーバーに戻った時には、子どもたちの姿はちょっぴりたくましく見えました。


引率をした小学部学部主事・下村先生は言います。
「事前にパドルの使い方などの学習はしてきたとはいえ、本当に初めての挑戦でした。桟橋を渡る時も恐々とした様子でしたが、指導を受けながら『ああ、こうやって漕ぐんだ!』と理解する様子も見受けられ、本当によく漕ぎきったなという思いです。今後もぜひ参加させていただきたいと思います!」
非日常の体験を終え、どこか誇らしげな表情をした子どもたち。秋らしい柔らかな日差しを受けてキラキラと輝く湖面に負けない、格別な笑顔が印象的でした。後日、SHIPMANには子どもたちからの寄せ書きも届いたそうです。
水上で仲間を思いやり、共に協力をして行動をすることは、日常生活にも通じており、コミュニケーションを図る上でも役立つというSHIPMANの城田さん。改めて休眠預金を活用した取り組みや今後の活動などについて伺いました。
風から、そして波から学ぶ。非日常の体験を子どもたちに届けたい!
「この青年の家は社会教育施設として、“来て!見て!やって!感動を!!”をテーマに昭和36年に発足しました。浜松は工場の町。当時の若い工員さんたちによる青年団が交流の場として活用していたんです。指定管理者として運営に携わったのは約8年前(2013年)。私たちが得意とする海洋活動を中心に、年齢、性別、そして国籍を問わず、誰でも利用できるイベントや体験学習を始めたんです」

城田さんは前職であるヤマハ発動機時代に培った経験を活かし、2003年にSHIPMANを立ち上げると同時に「浜名湖海の駅連絡会」で救助艇の手配などのボランティア活動にも従事してきました。浜名湖は浜松市と湖西市に跨る汽水湖(区分は二級河川)。水難事故などが起こった際に管轄である県警よりも素早く最寄りのマリーナから救助に行けるよう取り組んでいたそうです。しかし2010年に悲劇が起こります。一人の少女が湖畔での体験学習の際に亡くなってしまったのです。
「安易な任命が最悪の事故に繋がります。だからこそ、『How to=方法や手順』だけではなく、常に『Why=なぜ?』を基本に、会話をしながら活動することが重要です。そうした点を踏まえて、私たちSHIPMANのスタッフは知識や技術を伝えるインストラクターを超えた、活動の価値や意味をも伝えていくインタープリターとして取り組むことにしています。指定管理業務は水辺に関するプロでなければできません」

事故は絶対に起こしてはいけない。悲しく、また悔しい思いをしたからこそ、強い意志と使命感を持って、安全で安心な水辺の活動を目指す城田さん。スタッフと共にさまざまな訓練の日々を送り、再び浜名湖畔で体験学習が行えるようになりました。
小さなことから一歩ずつ取り組む。地域との連携で実現する支援活動
「休眠預金活用事業に手を挙げたのは、水辺の活動を通じて非日常的な体験を子どもたちにしてもらいたいと思ったことがきっかけです。特に、家族と十分なコミュニケーションを図ることが難しい子やさまざまな事情から殻に閉じこもっている子、あるいは障害を持つ子たちのために何かできないかとずっと考えてきました。子どもたちが気軽に訪れてSUPを楽しんだり、釣りをしたり。まずは徒歩や自転車で来られる範囲に住んでいる課題を抱えた子どもたちから漏らさず受け入れて行こうと、地元の小中学校の先生方にも協力を仰いでいます」
そんな取り組みの中、コロナウイルス感染症の蔓延を受けて県内外から年間約3万8000人が訪れていた青年の家も利用者が激減。城田さんは登校することもできず、居場所を失ってしまった地域の子どもたちを青年の家で預かる決断をします。その活動は施設内での学習だけではなく、駅のペンキ塗りや児童公園の草刈りなど、多岐にわたりました。
「近隣地域だけでなく、少し離れた街からも子どもたちが来るんです。青年の家は開放さえしていれば、誰でも利用できますからね。延べ200人の子どもたちを相手に、海洋指導員や元教職員、現役の校長先生まで、多くの人たちの協力を得て活動をしていました」
まさに草の根的な取り組みを経て、城田さんは地域とも連携し、さまざまな課題をクリアしてきました。休眠預金を活用した日々の活動から感じた今後の目指すべき方向はどのようなものなのでしょうか。

体験格差のない社会を目指して漕ぎ進むSHIPMAN
「特別支援学校はもちろん、不登校の子どもたちにも焦点をあててた活動をしたいですね。既に4年ほど前から地元の教職員を集めて水辺での活動を中心にさまざまな研修を定期的に行なっています。休眠預金活用事業の中長期計画の一環として、現在の取り組みや活動を、地域と連携しながら社会に向けて周知させることを目指して活動しています」
学校という場所を離れても子どもたちがいつでも帰れる場所をつくるべく、日々奔走している城田さん。昨今、注目を集める総合的な学習への取り組みにもチャレンジし、指導する側の意識改革にも余念がありません。またこうした活動を通じて、年齢や性別関係なく学べる機会や場所を設け、単独では難しい事象も県域を超えて同じ思いを持つ同志と連携することで「取りこぼさない社会づくり」を実現したいと言います。
マリンスポーツをはじめとする海洋活動を武器に、水辺のインタープリターたちの飽くなき挑戦は続きます。
■資金分配団体POからのメッセージ
SHIPMANの強みは、やはり城田さんの海洋活動を通じた青少年育成にかける果てしない情熱です。休眠預金活用事業を遂行する上で立地、施設や設備を含め、青年の家は素晴らしい環境。自治体や地域との連携を築き、特別支援学校や訪れる各団体に安全かつ楽しめるという育成プログラムや次へ繋がる研修の実施が実現できているのは水辺のプロからこそ。「ダブルハルカヌー」を新たに制作することで「健常者と障害を持つ子どもたちの体験格差」という課題も乗り越え、格差解消を目指した取り組みは、まさに本事業の目的に沿った活動です。インクルーシブ社会である昨今、誰もが社会の一員として集える地域社会づくりに向け、城田さん率いるSHIPMANと共に歩み、課題に取り組んでいきたいと考えています。
(公益財団法人 ブルーシー・アンド・グリーンランド財団 / 遠藤卓男さん)
取材・執筆:天屋 詠
【事業基礎情報】
| 実行団体 | 有限会社SHIPMAN(静岡県浜松市) |
| 事業名 | 障害児等の体験格差解消事業〈2019年通常枠〉 |
| 活動対象地域 | 静岡県西部地区 |
| 資金分配団体 | 公益財団法人 ブルーシー・アンド・グリーンランド財団(B&G財団) |
| 採択助成事業 | 障害児等の体験格差解消事業 草の根活動支援事業・全国ブロック〈2019年度通常枠〉 |
【この記事の事業に関連する「優先的に解決すべき社会課題」】
1.子ども及び若者の支援に係る活動
(1)経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援
(2)日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援2.日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援(5)日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援
【この記事の事業に関連する「持続可能な開発目標(SDGs)」】
| 目標4【教育】 | 目標10【不平等】 | 目標11【持続可能な都市】 | 目標14【海洋資源】 |
|
|
|
|
現在JANPIAでは「2021年度 資金分配団体の公募〈通常枠・第2回〉(11月30日17時まで)|コロナ対応支援枠〈随時募集〉」を実施中です。申請をご検討中の皆さま向けに、20/21年度資金分配団体である認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ 三島理恵さんにお話を伺いました。
休眠預金活用事業に申請した背景を自団体の活動と合わせて教えてください。
むすびえは、2018年に全国に広がるこども食堂の支援をしようと立ち上がった団体です。申請当時は設立して3年目というまだまだよちよち歩きで組織基盤を整えている段階で、コロナ対応支援枠に申請をしました。ですから、「休眠預金の事業を通じて社会課題の解決をしていこう」と十分に組織の準備ができて申請をしたというわけではありませんでした。
一方で、コロナ禍となり、こども食堂が緊急支援の活動を各地域で始められていたこともあって、こども食堂側の支援ニーズも本当に急拡大していました。こども食堂を包括的に支援する必要性が高まっていたことを受けて、むすびえが「いつか休眠預金を活用して社会課題の解決に資するような事業展開を全国規模でできないかな」と考えていたこと、そしてコロナ対応緊急支援枠の助成期間が1年ということもあって、「まだよちよち歩きの中だけどチャレンジしてみよう」となったのが、申請をした背景になります。
コロナ対応緊急支援枠を経て、通常枠に申請した経緯を教えてください。
「コロナ対応緊急支援枠」で緊急の支援を行える一方で、1年の助成活動を行うだけでは、そんなに簡単には社会課題が解決しないことも痛感しておりました。また「通常枠」で3年間の助成事業を行うからこそ、社会課題解決に資する事業ができることも感じており、次第に3年間だからこその事業に一度チャレンジしてみたいという気持ちを持つようになりました。コロナ対応緊急支援枠で採択いただいたことを私たち自身の成功体験として捉えていたので、「こども食堂」のような草の根事業から「イノベーションの促進に挑戦してみたい」と思ったことが通常枠にチャレンジしたきっかけでした。
かつ、この休眠預金を活用する事業自体が「社会的な大きな実験」であるということが私たちの背中を後押ししてくれました。「こども食堂」は全国に五千カ所広がる活動で、それが政策制度の裏付け無く、全国にボランティア活動として広がっています。そういった現象を私たちはひとつのイノベーションと捉えています。休眠預金活用事業の「社会課題の解決をイノベイティブに革新的な手法で解決していく」というところと「草の根の活動のこども食堂」の掛け算で、こういった社会課題の解決に全国で取り組むみなさんといっしょに取り組んでいけるということが、この通常枠に申請をさせてもらった大きなきっかけになりました。
コロナ対応緊急支援枠と通常枠の事業の違いなど、実施してみて感じたことはありますか。
組織体制を強化しながら休眠預金活用事業を行っていた私たちにとっては、コロナ対応緊急支援枠は、最初のチャレンジにはちょうどいい枠組みだと実感しています。
2つの事業の大きな違いは、「通常枠」は一定のリスクを許容しつつ、最大の成果を目指すために評価がセットになっている点です。私たちは最初にコロナ対応緊急支援枠の1年間の事業をして、そこに触れながら次に通常枠の3年間の事業にチャレンジできたので、その事業の中で「評価の重要性」を痛感しながら、通常枠の事業を推し進めていけるというところは、とても大事なステップを踏めていると思っています。
もう一つの大きな違いは、評価を通じながら、セオリーの確認をし、プロセスも含めてチームメンバーと共有化するコミュニケーションツールになっていること、内部での浸透度合いの違いというところだと感じています。
また3年間の通常枠では、社会の課題に対して「自分たちがどういうアプローチをし、どういう結果が生み出され、失敗も含めて、成果が出ているのか」を社会へのフィードバックをしっかりとしていく大きな責任があるのも、コロナ緊急支援枠との大きな違いだと実感しています。
助成事業を通じて、よかったこと、苦労していることはどんなことがありますか。
「事業の推進」「体制の強化」「財源の確保」という3つの軸を休眠預金活用事業を通じながら実施できているということ自体が、まずとても良かったと思っています。他の助成事業ではなかなか無い3つの成長というところへのアプローチだったと思っています。
また、成果を最大化させていくためにも、波及効果を狙って取り組んでいくことは大事な視点だと思っています。その上で最初に取り組んだこととしては、「内部での共有の場」です。
まず私たちが「休眠預金活用事業を通じてどういったことを実現しようとしているのか」を内部に対してしっかり浸透させていくこと自体がひとつ大きな価値になります。
かつこの事業自体はJANPIA、資金分配団体、実行団体、三者の「イコールパートナー」という関係性があるというところも踏まえて、横連携の会議なども複数に実施できていることが良い変化だったと思っています。
苦労していることは、まず、事業を開始する前は「申請する時の書類が多かったということ」です。もう一つは、システムには苦戦しています。逆に苦戦しているからこそ実行団体のみなさんと「これちょっとわからないよね」という会話をしながら関係構築をできているというところは、苦労しながらもチームビルディングにつかえているかと思います。
一方で、休眠預金活用事業の特徴の一つであるJANPIAさんとイコールパートナーでもあることから、「苦労している」ということもJANPIAの方に率直にお伝えできること、そして一緒に悩み、解決策を見出そうという場を設けてくださいます。
そういう意味では、JANPIA、資金分配団体、実行団体がいっしょになってこの休眠預金を活用した事業を推進していくこと自体が、社会課題をいっしょに解決する日本の中でのチームであり、社会課題の解決、社会変革を促す上ですごく大事なことだと受け止めています。
申請を考えている方へメッセージをお願いします。
まず、この事業自体が大きな社会実験なので、「ぜひ、一緒にチャレンジしませんか?」とお誘いしたいと思います。申請前のことを思い出すと、不安だったり、私たちが手を挙げて大丈夫なんだろうか、という懸念もありました。私自身もやれるんだろうか、組織が体制として十分なんだろうかということも何度も悩みましたし、自分たちにとってはまだ早いんじゃないかということも、組織の中で様々に検討しました。
その上で、やはり「チャレンジしないことには当然採択されない」ですし、休眠預金活用事業にかかわる機会も得られないということで、私たちは手を挙げました。
もし悩んでいらっしゃるであれば、そのお気持ちはとってもわかりますが、休眠預金活用事業に出会ったのであれば、ぜひチャレンジしていただきたいなと思っています。
実際採択されたときの不安もたくさんあると思います。私たちも「どのように実走させていくんだろう」、「本当に3年間で自分たちが目指している見たいゴールを見られるんだろうか」、と様々な不安がありました。そんな中でむすびえがやってこられているのは、この休眠預金活用事業のひとつの特徴でもある私たちへの「伴走支援」をJANPIAのPOのみなさんがしてくださるという枠組みがあるからです。そこは通常の助成事業とはまったく違うところで、ある意味安心してチャレンジできる器がこの休眠預金活用事業だなあと実感しています。
また申請にあたって、団体の中で今後のビジョンについても検討するプロセスを踏まれると思いますので、それも大事な機会として捉えてチャレンジを検討いただけたら嬉しいなと思っています。
〈このインタビューはYouTubeで視聴可能です!〉
※この動画は公募説明会で上映したものです。
(取材日:2021年10月26日)
▽こども食堂支援センター・むすびえの採択事業はこちらからご確認いただけます。
現在JANPIAでは「2021年度 資金分配団体の公募〈通常枠・第2回〉」を実施中です(公募締切:2021年11月30日17時)。申請をご検討中の皆さま向けに、19/20/21年度資金分配団体である公益財団法人 長野県みらい基金 理事長 高橋 潤さんにお話を伺いました。
休眠預金活用事業に申請した背景を自団体の活動と合わせて教えてください。
長野県みらい基金は2012年に寄付を集め、NPOや市民活動へ支援をすることを目的に設立されました。ですので、公益活動に対して資金を見つけてお渡しする、というのは本業でした。所属している全国コミュニティ財団の研修などでも、助成事業のあり方などを共有していく中で、休眠預金活用のロビー活動や法整備などを知り、手を挙げることにしました。手を挙げる際、地域のコミュニティ財団として、いわば地域の目利きとして、その背景、課題から申請内容を絞り込みました。
具体的には、寄付募集サイト「長野県みらいベース」を6年間運営してきて見えてきた地域課題、「こども若者支援に関する実態調査」から見えてきた課題と団体のその姿、長野県内のこども支援ネットワーク構築から見えてきた課題、資源。また、具体的な伴走支援の必要性が見えてきました。
例えば、2017年には長野県が実施した「子育て家族実態調査」の生データを使って、県内各地でNPOの方々と読み解き会を十数回行いました。その中で、「行政がやっている子育て支援が、家庭・こどものニーズとマッチしていない」「市町村の支援施策がいわゆるグレーゾーンの家庭に届いていない、あるいはその家庭の方々がその施策を使っていない」ということが見えてきました。また、「こども支援は親支援であるはずが、こども、親とばらばらになっている」「親へのアプローチが非常に少ない、あるいはできていない」という課題も「子育て家族実態調査」の読み解き会で見えてきました。
休眠預金活用事業の申請に対応するかたちでも長野県各地でヒアリングを開催しました。6地域で56団体の参加があり、様々なニーズ、またそれぞれの団体が抱えている課題、また地域の課題等が見えてきました。
木曽地域では、山間地であるがゆえに本来の対象者に対して支援が届けられない、というような声が聞こえました。松本地域では、地域の空き家など負の資産を活用してコミュニティづくりをしたい、という声がありました。伊那地域では、中山間地での引きこもり等のこども・若者の居場所を作りたいけれどすごく難しい、という声が聞かれました。全県を通じて、障害者や引きこもりのこども・若者の地域参加の機会を作りたい、といった声を多く聞くことができました。
そういった地域の具体的なニーズ、課題を深堀りする中で申請内容が固まってきました。
実行団体の公募について丁寧に進められたとうかがいました。取り組まれたことを教えてください。
この後お話する伴走支援ですが、実は公募開始前から始まっていると思っています。
2019年度では、まだコロナの影響がなかったので、広い長野県ですが4ヶ所で会場を使って説明会を開きました。
説明会の内容は、実行団体公募について基本的なこと、長野県みらい基金がJANPIAに対して申請した事業内容について説明しました。また、具体的な長野県内の公募内容についてご説明しました。もうひとつ、その当時なかなか耳に聞かなかった事業評価、社会的インパクト評価についても一部、二部ということで説明をさせていただきました。
説明会場での時期を見ながら、スケジュールとして開始から申請締切までできる限り長い時間を取ろうと思いました。何故かというと、事前相談を積極的にしたい、そういう呼びかけをしたい、ということがあったからです。
結果、延べ、29団体。1回の面談が21団体、2回面談した団体が7団体、3回面談した団体も1団体ありました。最終的に、実際の申請は18団体ありました。
申請後ヒアリングが、次の大事な支援となります。
共通の訪問調査表を元に、申請書では読みきれない項目。例えば、実際の事業を行う人や代表者の話し方や人となり、その関係性なども現場に行って感じ取ります。また、事務所の雰囲気も重要です。実際の事業をする場所にも案内してもらい、その事業のニーズの確認、対象者の想定の妥当性、実現性、重要性などを現場に行って肌で読み取ってきました。
訪問してのヒアリングシート、それぞれの申請書、団体の関連資料を元に、審査会資料作成のために事務局側の読み解き会を行いました。
宮城の先輩コミュニティ財団である、さなぶりのPOに来ていただき、長野県みらい基金のPOと一緒に丸二日かけて、申請書などの読み解きをしました。POそれぞれが、それぞれの申請に点数、懸念点、良い点などを記したものをそれぞれ発表、集計し、POとしての視点、客観性、共感、事業の将来性などを検討していきました。そうした中で、客観的な審査会用のヒアリングシートができました。
実行団体の伴走支援の内容や工夫を教えてください。
他の資金分配団体はいわゆるウェブのチャットツールなどを活用していらっしゃる、ともお聞きしていますが、長野県は非常にアナログです。2019年度はPO2名が中心となりながら、全員で伴走支援に取り組みました。広い長野県ですが、丁寧に現場を訪ね、たくさんお話しし、一緒に見守り、ともに育つ、という姿勢でした。全体を見るチーフは私がしながら、もうひとりのPOと更に2名に、地域や事業分野の傾向を見ながら担当をしてもらいました。
たとえば農福連携の事業には農協出身のスタッフを。また、地理的な条件も考慮しました。全国区でない地域に根ざした資金分配団体であること、また、申請書にもそこを大きな訴求ポイントにしていましたので、しっかりとした布陣で行いました。担当が随時連絡をとったり実行団体を訪問して、顔の見える関係性を作り、事業の成功への実行力のみならず、リスク管理への備えもしていきました。
また、評価、ファンドレイジングには専門家も支援チームに加わってもらい、出口戦略も見据えました。
実行団体と私たちは、ある意味運命共同体、パートナーなわけです。家族であり、友人であり、共同経営者です。ですので、伴走支援はいわば、日常の関係性の中から感じ取ることが一番重要だと私は思っています。そして、うまく行っているときは、一緒に喜ぶ。困ったときは一緒に悩むことが大事だと思います。
助成事業を通じて、よかったこと、苦労していることはどんなことがありますか。
1年半が過ぎ、今、中間評価のまとめの真っ最中です。順調に行っている事業ばかりではありません。特に、2019年度事業はコロナを想定していない時期の事業計画、資金計画ですので、スタート直後、いきなり事業計画変更、コロナ対応の資金提供など、それもこれも私たちも実行団体も、もちろんJANPIAさんも初めてのことばかりで、その場で検討、対応、相談しながら、悩みながら手探りで行ってきました。
現在、事業の折り返し地点で、多くの団体はここまでで経験し学んだ中で、あと1年半の事業の道筋を見極めて、進んでいます。「足りないところを補う」「うまく行っているところをより厚くする」「困っている人へより活動が届くよう、居場所で待っていた事業をアウトリーチ型に変更する」など、皆が学びながら、「困っている人をより支える」「地域を少しでもよくする」「そのために変えていく」という力が強くなっているのを感じます。
嬉しいのは、それぞれの事業・団体の連携が生まれてきていることです。もちろん、私たちが連携の糸口を作ったり、関係づくりの場を作ったりもしていますが、それぞれの団体が足りないところをより強みのある団体がつながることで補い、そうすることで困難を抱えている人たちへのより丁寧でしっかりとした支援が生まれています。地域同士の支え合いができてきていることが、本当に頼もしいと感じています。
申請を考えている方へメッセージをお願いします。
皆さんが助成をしようとしている対象の方々を、是非とも強く想ってください。その方々がどういう事業に対してどういうアプローチをしているのか、どういう対象の人たちに対して何をやりたいのか、ということを資金分配団体がしっかり知ることで、いわゆる良い公募案件が生まれるのだと思います。普段皆さんがやっていることの足元をもう一度見つめ直すということで、いい申請ができるのではないかなと思っています。
〈このインタビューはYouTubeで視聴可能です!〉
※この動画は公募説明会で上映したものです。
(取材日:2021年10月25日)
▽長野県みらい基金の採択事業はこちらからご確認いただけます。
認定特定非営利活動法人 ミューズの夢(以下、ミューズの夢)は、ハンディの有無にかかわらず子どもたちに質の高い音楽とアートに触れる機会と、自由に表現できる環境をつくることを目指して活動してきました。コロナ禍で活動が制限され、子どもたちにも不安が広がるなか、「離れていても芸術に触れることができ、一緒に参加できる楽しいプロジェクトを」と、2020年度新型コロナウイルス対応緊急支援助成〈資金分配団体:公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン(以下、セーブ・ザ・チルドレン)〉を活用した取り組みを進めています。芸術監督を務める仁科彩さんに伺いました。
不安な時期だからこそ、芸術に触れる機会を
20年前、宮城県仙台市で設立されたミューズの夢は、2つの事業を柱に活動に取り組んでいます。ひとつは、それぞれの子どもの発達とニーズに寄り添った音楽やアートのサポート教室の運営。もうひとつは、県内のこども病院や特別支援学校などを訪れて音楽療法士による授業を行ったり、音楽に触れる機会の少ない子どもたちへプロによるコンサートを届けたりする訪問事業です。
「サポート教室には、さまざまなハンディを抱えた子どもたちが多く通っています。設立当初から通っている生徒さんのなかには、その間に成人された方もいて、皆さんと一緒に成長してきた活動なのです。一人ひとりの個性に寄り添うことと、個性が育まれる環境を誰もが持てるように心がけることを、何よりミューズの夢では大事にしてきました」と話すのは、ミューズの夢の芸術監督を務める仁科彩さん。仁科さんは日本と北米を拠点にする作曲家であり、音楽講師としても活躍されています。

しかし、全国的なコロナ感染拡大によって、ミューズの夢の活動も大きな影響を受けました。2020年春は4ケ月間にわたりすべての活動を休止。一旦は教室を再開したものの、2021年8月に宮城県に緊急事態宣言が出た際も、再び教室を休止せざるを得ませんでした。これまで病院や事業所、特別支援学校などで年間90回近く行っていた訪問事業も、再開のめどが立たないままです。
「コロナのことを理解できていないお子さんも、テレビのニュースや家族の様子から何か大変なことが起きていることを感じています。そのような中、外に出られなくなり家に閉じこもるなど、震災のトラウマを思わせる行動を見せたお子さんもいたのです」
さらに、訪問事業で訪れていた長期入院中の子どもたちが、コロナ禍で面会や外出が制限されていると聞いた仁科さんたちは、こうしたストレスの強い状況に置かれている子どもたちの様子が気がかりだったと言います。
そこで、「コロナ禍だからこそ遠隔でも参加でき、これまでのように音楽とアートに触れられるプロジェクトが必要なのではないか」という思いから、2020年8月にセーブ・ザ・チルドレンが資金分配団体となって実施した新型コロナウイルス対応緊急支援助成「社会的脆弱性の高い子どもの支援強化事業」に申請。その後、審査を経て採択され2020年末から始めた取り組みのひとつが「Kotori Project(コトリ・プロジェクト)」でした。
子どもたちから届いた、個性溢れるコトリたち
「Kotori Project」には、その名の通りコトリ(小鳥)をモチーフにしたロゴマークが使われています。これはアートプログラム全体を監修する米国在住のデザイナー・田村奈穂さんによるデザイン。テーマカラーを決めるときは、田村さんとミューズの夢の生徒さんたちやこども病院の元患者さんが何度もやりとりをしながら一緒に考えました。

コトリの線画をプリントした紙を、こども病院や特別支援学校、発達支援事業所など19か所に配布して、「もしあなたがトリだったら、どんなお洋服を着たいですか?」とデザイン作品を募集したところ、252名から約500作品が届きました。
ミューズの夢の生徒さんたち、東日本大震災で大きな被害を受けたエリアにある放課後デイケアに通う子どもたち、入院中の子どもたちなどが参加しています。
「自宅や病院といった離れた場所からでも、子どもたち、ボランティアの若者、そして大人たちが『みんなで一緒に参加している感覚』をもてること。それが、プロジェクトを考えるときに一番意識したポイントでした」

作者の名前とともに作品をひとつずつ紹介するインスタグラム(SNS)ページには、さまざまな色や素材に彩られた小鳥たちがずらり! 大胆に塗られたカラフルな作品もあれば、布や木の枝を貼ったコラージュのような作品、また、真っ白な羽毛だけを使った現代アートのような作品もあり、その豊かな創造性にハッとさせられます。
「どれも発想が自由ですごいですよね。こんな素晴らしい作品が届くなんて、私たちも予想していませんでした。田村さんも『現代美術館に展示されていてもおかしくない!』と驚いたほどです」
仁科さんは、「この子の才能を評価していただいた事は初めてです」とある生徒さんのお母さんが嬉しそうな様子で話してくれたことも印象に残ったそうです。
「子どもたちは絵を描くことが楽しいだけでなく、お母さんが『すごいね、すごいね』と喜んでくれるので、その様子を見てさらに嬉しくなる。そして、また力作を描いてくれるんです」
インスタグラムのページでは、音楽に携わる世界中の中高生や大学生から募集したオリジナル音楽が流れる動画も紹介していて、東北の子どもたちが描くアートと海外の若者たちが作った音楽とのコラボレーションも生まれています。
絵本のユニバーサルデザインと「心のケア」
このKotori Projectはさらに発展し、現在では子どもたちから集まった作品で絵本をつくる取り組みも進んでいます。
「作品があまりに素晴らしいので展覧会をしたいという話が出たのですが、いまはコロナで難しい。そこで 絵本を作ろうということになったのです」
絵本のストーリーは音楽講師や音楽療法士によるオリジナルで、一羽のコトリのもとに楽しい仲間が集まってくるという内容です。弱視の子どもでも読みやすいようにデザインを工夫したり、発語療育に使われている言葉を文章に取り込んだり、音声でも楽しめるオーディオブックにするなど、「絵本のユニバーサルデザイン」を目指しています。
「どんな子どもも楽しめる絵本にしてほしいというのは、ミューズの夢の保護者の方たちからのリクエストでもありました。絵本が完成したら参加した子どもたちや子ども病院、特別支援学校などに配布予定です。この絵本を通じて、あとでコロナ禍を振り返ったときにつらかった体験だけでなく、楽しかった体験も思い出して自信にしてほしい」

さらに、ミューズの夢では子どもたちの「心のケア」に取り組む活動を開始。
「コロナ禍が子どもの東日本大震災のトラウマを引き起こすケースもあったという話を聞き、自然災害やコロナなどの緊急事態が起きたときに、子ども自身や周りにいる大人が読むことでトラウマケアにつながるような絵本の執筆を、臨床心理士であるUdeni Appuhamilage 先生に依頼したのです」
先ほどの子どもたちの作品を使った絵本は3歳から対象ですが、心のケアのための絵本は小学校中学年以上向け。Udeni先生によって英語で書かれた物語を、さまざまなボランティアさんの手で日本語をはじめ多言語に翻訳し、世界中どこからでもダウンロードできるようにする計画です。
「心のケアの絵本制作にあたっては、資金分配団体であるセーブ・ザ・チルドレンが開催する『子どものための心理的応急処置』というワークショップを受けたことが大きな参考になりました。子どもの権利に取り組んできたセーブ・ザ・チルドレンが伴走してくださることで、事業がより深まったと感じています」

事業を通じて感じた「子どもたちへの敬意」
ミューズの夢では、このほかにも助成事業の一環として、コロナ禍で訪問事業ができない代わりに音楽配信を行う「Strings of Love」などの取り組みも行っています。
仁科さんは、コロナ禍でも変わらない子どもたちの芸術に向かう熱意と誠実さ、そして周りを思いやる気持ちから、私たちが学ぶべきことがたくさんあるのではないかと話します。
「ハンディを抱えた子どもたちはサポートを受ける立場になることが多いのですが、実際にはどんな子どもも自分自身を立て直すだけの力を持っています。音楽やアートに触れて自分の表現を見つけることが、そうした『生きる力』につながります。私たちにできるのは、その機会を共に創り続けること。そして、生み出されたアートや音楽を世の中に発信していくことで、ハンディを抱えた子どもたちの教育や文化的な権利がもっと見直されてほしいと思っています」
■休眠預金活用事業に参画しての感想は?
今回、休眠預金活用事業として助成をいただいていることが信頼になって、県内の他団体とのネットワークづくりもスムーズに進めることができたと感じています。また、子どもの権利に取り組んできたセーブ・ザ・チルドレンには資金分配団体として伴走していただき、的確なアドバイスをいただきながら事業を進めてきました。何より「一緒に子どもたちのいる環境をよくしましょう!」といつも仰ってくださることが嬉しく、セーブ・ザ・チルドレンとミューズの夢の相乗効果で、Kotori Projectを展開することができたのだと思っています。(仁科さん)
■資金分配団体POからのメッセージ
ミューズの夢のみなさんは、「どんな障害や病気があっても、すべての子どもに芸術を楽しむ権利がある」と熱意をもって今回の事業に取り組んでくださっており、かつ大きな成果もあげています。今回は新型コロナウイルス感染症流行下での緊急助成事業でしたが、社会から周縁化されてしまっている子どもたちに芸術面での支援や機会が必要だということを、これから広く日本社会に伝えていくきっかけになる大事な取り組みだと思っています。(公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 鳥塚さん)
取材・執筆:中村未絵
【事業基礎情報】
| 実行団体 | 認定特定非営利活動法人 ミューズの夢 |
| 事業名 | 緊急事態下における子ども及び若者による芸術創造活動の支援事業 副題:芸術教育のユニバーサルデザインとトラウマケアに関する取り組み |
| 活動対象地域 | 全国 |
| 資金分配団体 | 公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
| 採択助成事業 | 『社会的脆弱性の高い子どもの支援強化事業』 〈2020年新型コロナウイルス対応緊急支援助成〉 |