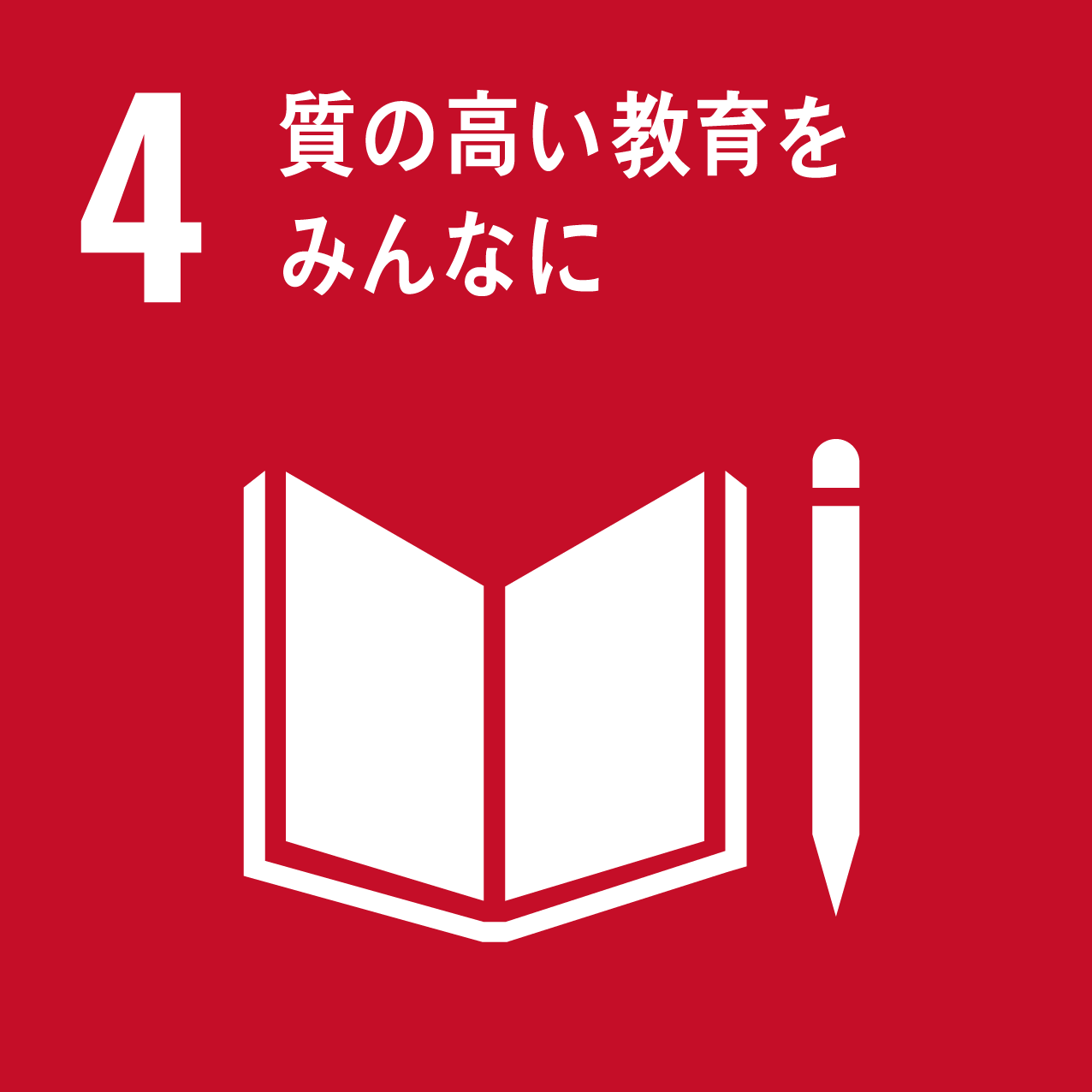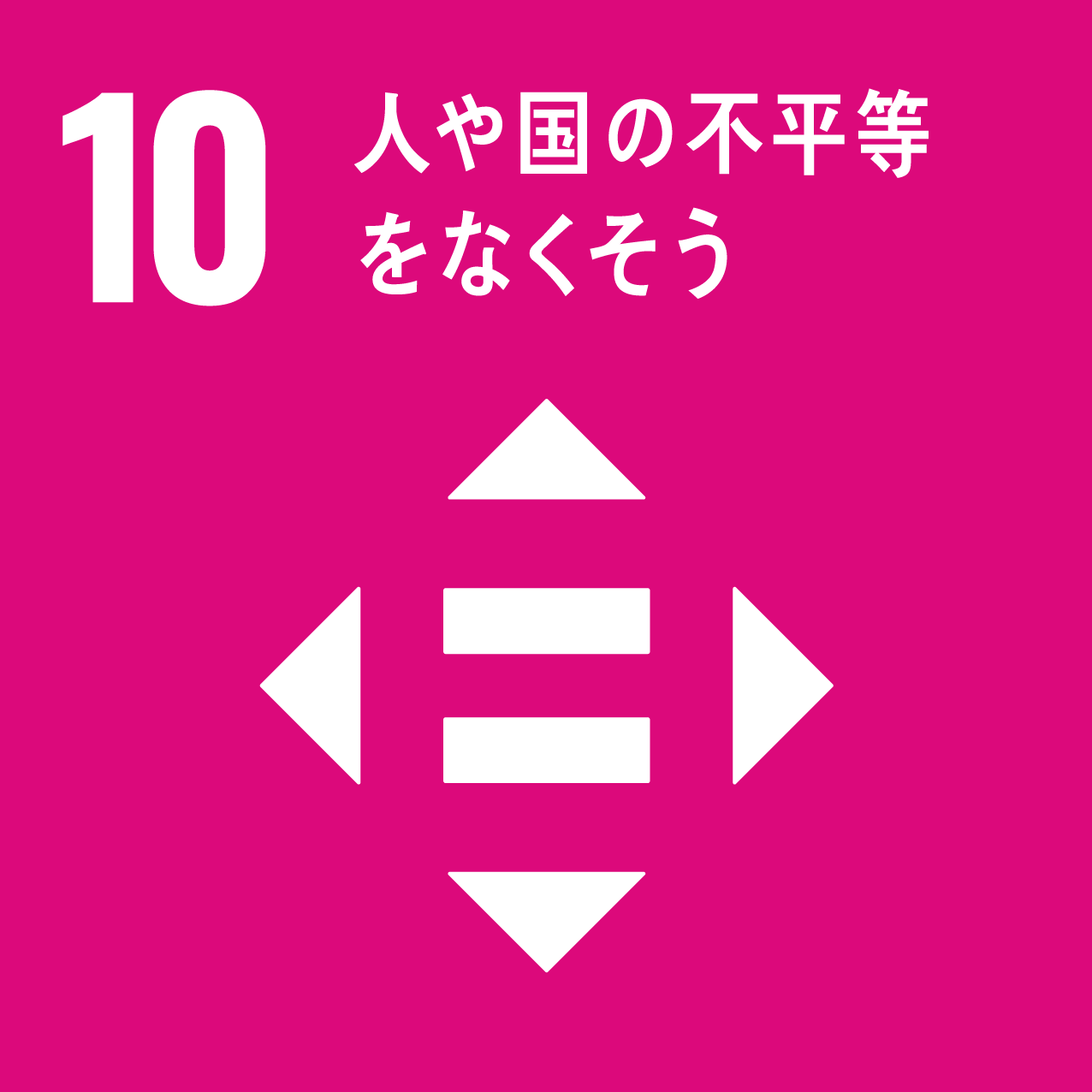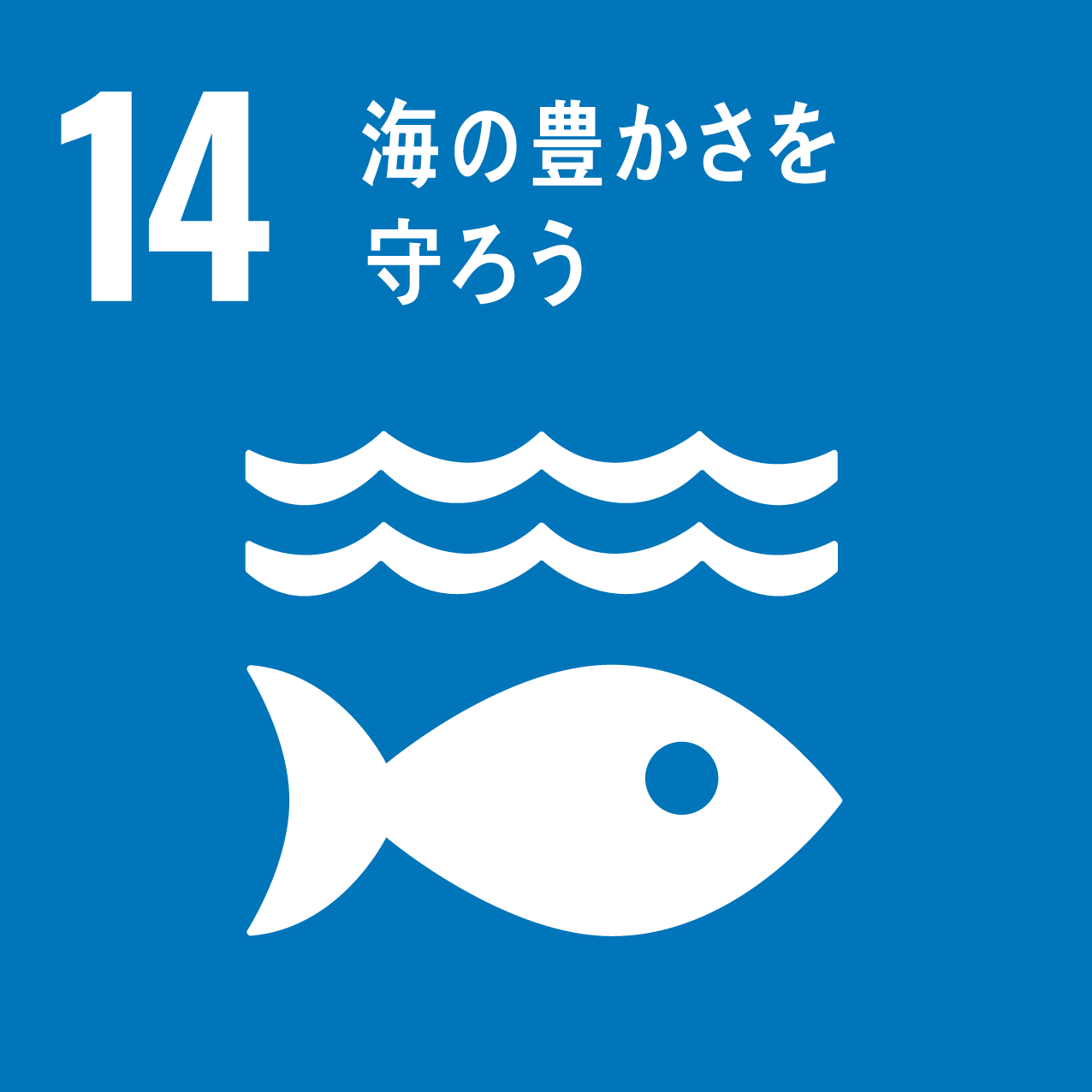今回の活動スナップは、株式会社よしもとラフ&ピース(資金分配団体:公益財団法人 九州経済調査協会)。BSよしもとで放映された『島ぜんぶでうむさんラブ「沖縄をソーシャルビジネスアイランドに!」』の動画が5本公開されましたので紹介します!
活動の概要
沖縄県41 市町村におけるソーシャルビジネスの起業支援・普及啓発を目的としたインキュベーション事業。那覇市に開設するインキュベーションセンターを拠点に、県内41 市町村でソーシャルビジネスの講習ワークショップ「出張インキュベーション(起業支援)」を実施。同時に、 2021 年12 月開局予定のBS 放送局「よしもとBS チャンネル」と連動し、支援対象ビジネスを同局にて番組化することで、事業を展開するモデルを生み出す。
活動スナップ
第1回
ソーシャルビジネスって何だろう?
「沖縄をソーシャルビジネスアイランドに!」をコンセプトに沖縄県内でソーシャルビジネスの普及活動を行っている『島ぜんぶでうむさんラブ』の取り組みを、番組ナビゲーターのハイビスカスパーティーちあきが紹介します!
ソーシャルビジネスとはどういうものか?を九州大学の教授であり、一般社団法人ユヌスジャパン代表理事の岡田昌治先生に教えていただきました!
※YouTubeの概要より転載
第2回
4月に行われた『島ラブ祭』の様子をお届けします。
前回に引き続きムハマド・ユヌス博士よりメッセージも頂きました!
※YouTubeの概要より転載
第3回
#3では、地元沖縄で長年人材育成に取り組み、今回の事業でもソーシャルビジネスの創出に共に活動している、株式会社うむさんラボの比屋根隆さんにお話をお聞きしています。また、島ラブアカデミー参加者のそれぞれの想いもお伝えしています。
第4回
#4からは島ラブ祭2022で発表されたそれぞれの事業を紹介します。今回は沖縄住みます芸人のありんくりんの比嘉竜太さんが登場しています。小学生を対象とした「漫才ワークショップ」を通して伝えたい想いとは?
第5回
さし草の魅力を発信しているさし草屋さんの活動を紹介します!
※YouTubeの概要より転載
休眠預金活用事業として実施されている「甲信地域支援と地域資源連携事業」。資金分配団体である「認定NPO法人 富士山クラブ」「公益財団法人長野県みらい基金」のコンソーシアムと、山梨県・長野県で子どもや若者たちを含む、困り事を抱えた人々が自ら課題解決できる力を持てる環境づくりに挑む5つの実行団体でこの事業を進めています。山梨県域で活動している3つの実行団体に、資金分配団体のプログラムオフィサー(以下、PO)とJANPIAのPOが視察もかねて訪問した様子を、レポートします。
NPO×自分の生業でゼロからイチを生む!〈河原部社〉
はじめの訪問先は山梨県韮崎市で活動する「NPO法人河原部社」。
河原部社は「やって、みせる」というポリシーのもと2016年に活動をスタートさせました。団体メンバーの平均年齢は30歳。代表理事を務める西田遥さんを中心に、地域おこし協力隊として参加するメンバーを加え、地元の有志8名で韮崎市を盛り上げようと取り組んでいます。

設立当時からビジネスとして「収益をきちんと得られる仕組みづくり」を視野に、「NPO×自分の生業」という働き方のスタンスを保ちながら活動。参加する若者たちがそれぞれのスキルを持ち寄り、活かしながら、社会に対して面白いことを仕掛けていこうと考えています。
既に行政の委託事業として、いくつかの実績を持つ河原部社。JR韮崎駅前にある青少年育成プラザ「Miacis(ミアキス)」の運営は5年目を迎え、立ち上げ当時から利用していた中高生が同社に入社したり、また韮崎市役所に就職したりするなど、後進の育成にも成功。同時にローカルメディア「にらレバ」を運営し、若者向けに地元に特化した情報を発信することで、就職や結婚なども含め、今後の人生の選択肢に「地元」を入れてもらえるようにと継続的に取り組んでいます。
「街のために何かチャレンジしたいという、僕らと同世代の若者がとても多いんです。若者のチャレンジをぜひ現実化したい、さらに自立できるようにビジネスとしても確立させてほしい。そこでまずは私たち自身の団体の組織基盤を強化するために休眠預金活用事業に申請させていただきました。」そう話す西田さん。

彼らが休眠預金活用事業として取り組むのは、「ニラサキサラニ 実践型若者プレイヤーズ育成プロジェクト」。
廃業をしたガソリンスタンドを拠点とし、「ゼロからイチを生み出す経験ができる場づくり」を目標にしています。「プレイヤー」と呼ばれる賛同者と共に活動をはじめるために、現在は本プロジェクトの一つとして「WORKSPACE TUM」の立ち上げと、これらに付随したイベントの企画を急ピッチで進めています。今後はSNSなどを利用し、オンラインでも参加者(TUM MATE)を増やす予定だと本プロジェクトのリーダー・本田美月さんはいいます。


「TUMという名前には、経験や知識を積む場所、そして掛け算を意味する積から『アイデアが掛け合わさる場所』という意味を込めています。TUM MATEの皆さんと共に、さまざまな職域の方達との交流を経て、社会に対する思いを実現へと導くコミュニティを運営していく予定です。」

今回の訪問では、資金分配団体とJANPIAのPOと共に活動進捗を話しながら、どのように収益を上げるかで終わらず、一つ先の視点を継続して持ち、さらにこのプロジェクトを通じて力をつけてソーシャルビジネスなどへのステップアップを目指していくことを改めて共有できた皆さん。何もないところからスタートアップして、大きな団体として行政も巻き込み活動していくというサクセスストリーを描き、「韮崎モデル」として他県域にも広がることを願っています。
「社会的処方+学習支援」で地域課題に挑む〈ボンドプレイス〉

次に訪れたのは、同県南アルプス市の古民家を活動の拠点とするNPO法人bond place(ボンドプレイス)。「接着剤のボンド」と「場所を意味するプレイス」という意味を持つ同団体。現在、行政からの委託事業の一つとして南アルプス市、山梨市と辛い思いを抱えた子どもや若者たちに向けた「居場所づくりの事業」を中心に、孤独や孤立といった問題を抱える人に対してどのようなアプローチができるかを検討し、学習支援や子ども食堂などの利用を促す取り組みをおこなっています。そんな彼らが活動を通じて体感しているのは、こうした支援活動が各市町村単位での対応であること、また福祉など特定の分野に限られた課題設定となりがちであることでした。

「これまで公的な支援においてキャッチできなかった人や物事も多くあります。私たちは、いろいろなセーフティネットに助けられる機会を「学習支援」という入口から取り組んでいこうと考えました。個々が強くなるためではなく、その人たちの環境自体が変わっていくことに対してのアプローチを重要視し、山梨県から社会や環境を変えていきたい。そこで辿り着いたのが『社会的処方』というテーマでした」
そう話すのは理事を務める芦澤郁哉さん。「社会的処方」とは医療機関の取り組みの一つで、薬などの処方だけでなく、社会的な繋がりも処方するというもの。例えば、郵便局に隣接した場所で年金受給日に看護師さんが高齢者の健康相談に乗ったり、地域の資源を最大限に活用して、悩みを抱える人々と触れ合うことなどが挙げられます。こうした考えを実社会に置き換え、1つの分野だけでは解決し難い社会課題においてファシリテーターという役割を担い、「学び」という部分からさまざまな領域の人々を繋ぎ、地域の困りごとを解決する。法的な窓口ばかりに頼るのではなく、自分達から困っている人に出会いに行こうというのが今回の事業、「社会的処方を目指した生態系構築モデル」です。休眠預金を活用し、委託事業としてではなく、自主的な事業として確立できるようチャレンジすることになりました。

2020年度にスタートした「社会的処方の学校」の講座では、分野を問わず参加者自身が自然と行動に移せる仲間づくりを目指し、3〜4人のチームに分かれて課題に取り組んできました。。相手の困りごとをこちら側が勝手に判断をしないことを念頭に、悩みを持つ本人との関係性を深め、向き合い方を捉え直して解決へと導く。さらに「(人が)力を持てる地域、環境づくり」を目指し、対象者が自らの力で歩き出せる環境を作るためにできることを考え、実践へと落とし込んでいく流れです。
同時に社会的処方を実践する上で、当事者に必要な人、物事、環境などを繋ぐ役割「リンクワーカー」の育成を目指します。
開講以来、全5回の講座を終えた今、同様の意味合いを持ちながらも異なる表現ですれ違いを起こしていた事柄も丁寧に言葉を紡ぐことで、専門領域を超え新たな視点からサポートを実現するという強い意識が芽生えているそうです。問題意識を持ちながら、今ある行政制度を底上げする。より良い効果が出る道の模索が続いています。

本プロジェクトのゴールである3年後を目指し、今後はより視点を広げた環境づくりに取り組み、純粋に社会的処方という考えや、リンクワーカーとして担うべきことを定義づけることに注力していくとのこと。課題解決に向けて、幅広い世代のスタッフと分野を超えた参加者の皆さんが力強く歩みを進めている様子が印象的でした。
リユースお弁当箱で子育てママの孤立を救おう!〈スペースふう〉
最後は、子育て中のママさんたちを「食」を通じて応援する認定NPO法人スペースふうを訪れました。1999年に小さなリサイクルショップをオープンさせ、以来、南巨摩郡富士川町を拠点に地域活性や女性の自立支援などを中心に活動をしています。これまでの活動はもちろん、昨今の取り組みの中でスペースふうのメンバーが強く感じ取っていたのは、やはり「孤独」、「孤立」という問題。それらは、コロナ禍を受けて加速傾向にあります。自分が本当に必要とされているのか…、そんな不安を払拭しつつ、自分を大切にできる場所づくりにチャレンジすることにしました。そこで誕生したのが、休眠預金を活用した「リユースお弁当箱がつなぐ地域デザイン事業」です。産後のママさんをはじめ、子育て家庭に向けて「hottos(ホットス)プロジェクト」を立ち上げ、リユース食器などを使用した宅配お弁当サービスをスタートさせました。

特筆すべきは、リユースのお弁当箱(食器類)のメンテナンス、そしてお弁当を包む可愛らしい手ぬぐいをはじめ、hottosのロゴ、LINEの運用など、活動の中枢を子育て中のママさんたちが担っていること。長時間の労働が難しいママさんたちに、それぞれの強みを活かした新しい仕事、居場所を提供することで社会との繋がりや会話が生まれているのだそうです。

事務局の長池伸子さんはいいます。 「活動するための準備や特別な知識がない状態でも、社会課題と向き合うチャンスと思いを受け入れ、実践しながら活動に取り組めるのは休眠預金だからこそ。担当POのアドバイスを受けながら、近隣県域のNPO仲間等とも連携して一緒にゴールを目指せる環境が活動の支えになっています。 これからも誰に頼れば良いか分からないなど、気持ちや環境に余裕がない人をそっと見守る存在として、いい意味で新しい形のお節介をしていきたいですね」
美味しいと評判のお弁当は、南アルプス市で活動する「Public House モモ」によるもの。注文は予約制で、祝日を除く毎週木曜日と金曜日にスタッフが手渡しでお届けしています。利用費用は、なんと一食100円。各種アレルギーなどにも対応し、肉や野菜など、種類豊富で彩りも豊かなおかず類は食べるのはもちろん、見た目にも楽しい気持ちになります。現在の利用者は富士川町に住む11名の新米ママさんや子育て家庭。まだまだ少数ではあるものの、「産後の大変な時に本当に助かったし、優しい言葉もかけてもらえてホッとした」といった声が届いています。連絡手段には、利用者世代のママさんが使いやすいLINEを導入し、繋がりやすさも工夫。利用者さんからの口コミで広がることの重要性を体感しているそうです。


現在は子育て世代を中心としているものの、今後はその枠を広げ、お弁当を通じたコミュニケーションから子どもたちや若者が社会課題を解決する力を持てる地域づくり、さらには次世代への橋渡しにも挑みたいという長池さん。本プロジェクトを遂行する上で、こうした活動の過程を開示しながら持続可能な組織として自立し、新たなビジネスモデルとしての確立が目下の課題であることを改めて担当POとの対話で再確認しました。
キーワードは「お弁当を開けた時のホッとする瞬間」。「孤独」や「孤立」から多くの人を見守る事業モデルに今後も注目していきたいと思います。
【事業基礎情報】
| 資金分配団体 | 認定特定非営利活動法人 富士山クラブコンソーシアム構成団体:公益財団法人長野県みらい基金 |
| 助成事業 | 甲信地域支援と地域資源連携事業 ~こども若者が自ら課題を解決する力を持てる地域づくり事業~ |
| 活動対象地域 | 甲信地域(山梨県・長野県) |
| 実行団体 | ★特定非営利活動法人 河原部社 ★特定非営利活動法人 bond place ★認定特定非営利活動法人 スペースふう 特定非営利活動法人 こどもの未来をかんがえる会 一般社団法人 信州上田里山文化推進協会(旧:杜の風舎) ★印の団体が今回の訪問先です。 |
https://youtu.be/MgpL5cfJQuU
https://youtu.be/D3iYli3fryQ
https://youtu.be/xuWh0PGJwG0
https://youtu.be/QdI2xAGTF28
https://youtu.be/NZkSyVRFzMs
https://youtu.be/nG7_1aYNxtE
https://youtu.be/P_xF_0FHOEY
https://youtu.be/TfMu06OPhgo
https://youtu.be/-cD7yX6cr_8
https://youtu.be/t67mn-Z_od4
https://youtu.be/2CWXOo-NTCI
https://youtu.be/3cJcU6JrVtc
https://youtu.be/DtDrq8onets
https://youtu.be/IskasYXdo4U
https://youtu.be/iJS77RimQfE
https://youtu.be/QAQCwKrtBG0
https://youtu.be/hilch1u2ntI
https://youtu.be/wVLxAUN221M
https://youtu.be/Zqi0ZatKAVY
https://youtu.be/Dowdasi4ORM
https://youtu.be/rp710OEBRSA
https://youtu.be/BCzJKHP5H2Q
https://youtu.be/EuIxRJUw5Ms
https://youtu.be/p7xFxTVvscc
https://youtu.be/p4XjqNGo3TQ
https://youtu.be/BBikeftb2qI
https://youtu.be/WS89S3IVjuI
https://youtu.be/FyeSC12K8lA
「ダブルハルカヌーって安全性が高いんですよ」。そう爽やかな笑顔で話してくださったのは、有限会社SHIPMANの代表取締役を務める城田守さん。2019年度通常枠〈資金分配団体:公益財団法人 ブルーシー・アンド・グリーンランド財団〉の実行団体として、活動拠点である静岡県立三ヶ日青年の家(以下、青年の家)を舞台に浜名湖畔で体験格差をなくすべく、水辺の活動やさまざまな支援に取り組んでいます。今回は、日本でここにしかない「ダブルハルカヌー」に特別支援学校の子どもたちが挑戦!その体験学習の様子、そして休眠預金を活用したSHIPMANの取り組みなどを取材しました。
ダブルハルカヌーに挑戦。美しい浜名湖をみんなで駆け抜けよう
11月初旬、浜松市内の特別支援学校の生徒たちが三ヶ日青年の家を訪れていました。集まっていたのは、小学4年生と5年生の男女8名。聴覚障害を持つ児童たちです。彼らが今日体験するのは「ダブルハルカヌー」。浜名湖畔で、日頃、触れ合う機会のない水辺での体験学習に挑みます。

体育着姿の子どもたちが集まったのは、マリーナ広場にある艇庫(ボート倉庫)。その一角で、まずは水辺での活動の際に注意すべきことや漕ぎ方などについて学びます。大きなポイントは3つ。1つ目はSHIPMANの指導員や先生たちの話をよく聞くこと。2つ目はできる限り大きな声を出す。そして3つ目は素早い行動を心掛けること。水上ではちょっとした甘えが事故に繋がるため、一緒に乗船する艇長の指示に従って行動しなくてはなりません。続いて、水辺の活動では着用が欠かせないライフジャケットについて指導を受けます。
「ライフジャケットは必ず体が浮くようにできています。もし水の中に落ちてしまったら、体育座りのようにできるだけ小さな姿勢を保って救助を待ちます。落ち着いて襟元をしっかり掴んで下にぐっと引っ張りながら上を向いて呼吸を確保してください。暴れたり、泳いだりすると体力を消耗するので、静かに救助を待つよう注意しましょう」

着用したライフジャケットを触ってみたり、友だちと話してみたり、緊張した表情を浮かべつつも、どこか楽しげな様子の子どもたち。次は艇長の指導でパドルの持ち方や漕ぎ方を学びます。元気な挨拶が艇庫いっぱいに広がると、木製パドルが順番に配られました。いろいろ試してみたいところですが、ここはぐっと我慢!
「今、みんなに配ったのが、カヌーを漕ぐときに使用するパドルです。大事な道具なので杖にしたり、振り回したりしてパドルを傷つけたり、周りのお友だちに怪我をさせないように注意しましょう!」
艇長の両脇で引率の先生が手話で説明をします。口の動きと手話で持ち方を学ぶと、子どもたちは素早く行動。ダブルハルカヌーは二層のカヌーが並行に繋がれた仕様のため、乗船する場所によってパドルの持ち方が異なります。向かって右側の列は左手で上部の三角部分を握り、右手で一番細い部分を持ちます。左側の列は、その逆です。しっかり持つことができたら、いよいよ漕ぎ方の練習。友だちにぶつからないように距離を保ちます。
「漕ぐ時は “1、2、ソーレ!” という掛け声に合わせてパドルを動かします。艇長が1、2、みんなはソーレ!です。パドルを戻す時は後ろの人に水がかからないように、水からスッと抜くようなイメージ。ちょっとみんなで練習してみましょう!」

少し照れくさそうにしていた子もいつの間にかどんどん大きな声に。テンポ良くパドルを動かしながらイメージを膨らませます。しっかり準備ができたら、ここで持参した小さなタッパーに補聴器や人工内耳をしまいます。子どもたちは水辺での活動やプール学習の際はもちろん、雨の日も傘がない時は必ず装具を外すといいます。聞こえにくく不安に感じる際は周囲の状況をよく見ることに意識を向けるなど、日頃の自立活動の時間を通じて学んでいます。

水上で学ぶ「思いやり」と「協力」の姿勢
艇長に続いて艇庫を出ると、雄大な浜名湖が子どもたちを待っていました。ヨットハーバーに到着すると休眠預金を活用して購入したという真新しい桟橋から、指示に従ってダブルハルカヌーに乗船していきます。
浜名湖は海とは異なり、時折、すれ違う漁船による引き波以外は、大きな波もなく水面は穏やか。これまでに経験のない揺れに驚いて声を出す子もいましたが、ぐんぐん進むうちにいつの間にか掛け声も大きく、パドルも力強く揃った動きに。前にいる仲間の動きをよく見て、後ろの友だちのことを思いやり、協力して漕いだダブルハルカヌー。ヨットハーバーに戻った時には、子どもたちの姿はちょっぴりたくましく見えました。


引率をした小学部学部主事・下村先生は言います。
「事前にパドルの使い方などの学習はしてきたとはいえ、本当に初めての挑戦でした。桟橋を渡る時も恐々とした様子でしたが、指導を受けながら『ああ、こうやって漕ぐんだ!』と理解する様子も見受けられ、本当によく漕ぎきったなという思いです。今後もぜひ参加させていただきたいと思います!」
非日常の体験を終え、どこか誇らしげな表情をした子どもたち。秋らしい柔らかな日差しを受けてキラキラと輝く湖面に負けない、格別な笑顔が印象的でした。後日、SHIPMANには子どもたちからの寄せ書きも届いたそうです。
水上で仲間を思いやり、共に協力をして行動をすることは、日常生活にも通じており、コミュニケーションを図る上でも役立つというSHIPMANの城田さん。改めて休眠預金を活用した取り組みや今後の活動などについて伺いました。
風から、そして波から学ぶ。非日常の体験を子どもたちに届けたい!
「この青年の家は社会教育施設として、“来て!見て!やって!感動を!!”をテーマに昭和36年に発足しました。浜松は工場の町。当時の若い工員さんたちによる青年団が交流の場として活用していたんです。指定管理者として運営に携わったのは約8年前(2013年)。私たちが得意とする海洋活動を中心に、年齢、性別、そして国籍を問わず、誰でも利用できるイベントや体験学習を始めたんです」

城田さんは前職であるヤマハ発動機時代に培った経験を活かし、2003年にSHIPMANを立ち上げると同時に「浜名湖海の駅連絡会」で救助艇の手配などのボランティア活動にも従事してきました。浜名湖は浜松市と湖西市に跨る汽水湖(区分は二級河川)。水難事故などが起こった際に管轄である県警よりも素早く最寄りのマリーナから救助に行けるよう取り組んでいたそうです。しかし2010年に悲劇が起こります。一人の少女が湖畔での体験学習の際に亡くなってしまったのです。
「安易な任命が最悪の事故に繋がります。だからこそ、『How to=方法や手順』だけではなく、常に『Why=なぜ?』を基本に、会話をしながら活動することが重要です。そうした点を踏まえて、私たちSHIPMANのスタッフは知識や技術を伝えるインストラクターを超えた、活動の価値や意味をも伝えていくインタープリターとして取り組むことにしています。指定管理業務は水辺に関するプロでなければできません」

事故は絶対に起こしてはいけない。悲しく、また悔しい思いをしたからこそ、強い意志と使命感を持って、安全で安心な水辺の活動を目指す城田さん。スタッフと共にさまざまな訓練の日々を送り、再び浜名湖畔で体験学習が行えるようになりました。
小さなことから一歩ずつ取り組む。地域との連携で実現する支援活動
「休眠預金活用事業に手を挙げたのは、水辺の活動を通じて非日常的な体験を子どもたちにしてもらいたいと思ったことがきっかけです。特に、家族と十分なコミュニケーションを図ることが難しい子やさまざまな事情から殻に閉じこもっている子、あるいは障害を持つ子たちのために何かできないかとずっと考えてきました。子どもたちが気軽に訪れてSUPを楽しんだり、釣りをしたり。まずは徒歩や自転車で来られる範囲に住んでいる課題を抱えた子どもたちから漏らさず受け入れて行こうと、地元の小中学校の先生方にも協力を仰いでいます」
そんな取り組みの中、コロナウイルス感染症の蔓延を受けて県内外から年間約3万8000人が訪れていた青年の家も利用者が激減。城田さんは登校することもできず、居場所を失ってしまった地域の子どもたちを青年の家で預かる決断をします。その活動は施設内での学習だけではなく、駅のペンキ塗りや児童公園の草刈りなど、多岐にわたりました。
「近隣地域だけでなく、少し離れた街からも子どもたちが来るんです。青年の家は開放さえしていれば、誰でも利用できますからね。延べ200人の子どもたちを相手に、海洋指導員や元教職員、現役の校長先生まで、多くの人たちの協力を得て活動をしていました」
まさに草の根的な取り組みを経て、城田さんは地域とも連携し、さまざまな課題をクリアしてきました。休眠預金を活用した日々の活動から感じた今後の目指すべき方向はどのようなものなのでしょうか。

体験格差のない社会を目指して漕ぎ進むSHIPMAN
「特別支援学校はもちろん、不登校の子どもたちにも焦点をあててた活動をしたいですね。既に4年ほど前から地元の教職員を集めて水辺での活動を中心にさまざまな研修を定期的に行なっています。休眠預金活用事業の中長期計画の一環として、現在の取り組みや活動を、地域と連携しながら社会に向けて周知させることを目指して活動しています」
学校という場所を離れても子どもたちがいつでも帰れる場所をつくるべく、日々奔走している城田さん。昨今、注目を集める総合的な学習への取り組みにもチャレンジし、指導する側の意識改革にも余念がありません。またこうした活動を通じて、年齢や性別関係なく学べる機会や場所を設け、単独では難しい事象も県域を超えて同じ思いを持つ同志と連携することで「取りこぼさない社会づくり」を実現したいと言います。
マリンスポーツをはじめとする海洋活動を武器に、水辺のインタープリターたちの飽くなき挑戦は続きます。
■資金分配団体POからのメッセージ
SHIPMANの強みは、やはり城田さんの海洋活動を通じた青少年育成にかける果てしない情熱です。休眠預金活用事業を遂行する上で立地、施設や設備を含め、青年の家は素晴らしい環境。自治体や地域との連携を築き、特別支援学校や訪れる各団体に安全かつ楽しめるという育成プログラムや次へ繋がる研修の実施が実現できているのは水辺のプロからこそ。「ダブルハルカヌー」を新たに制作することで「健常者と障害を持つ子どもたちの体験格差」という課題も乗り越え、格差解消を目指した取り組みは、まさに本事業の目的に沿った活動です。インクルーシブ社会である昨今、誰もが社会の一員として集える地域社会づくりに向け、城田さん率いるSHIPMANと共に歩み、課題に取り組んでいきたいと考えています。
(公益財団法人 ブルーシー・アンド・グリーンランド財団 / 遠藤卓男さん)
取材・執筆:天屋 詠
【事業基礎情報】
| 実行団体 | 有限会社SHIPMAN(静岡県浜松市) |
| 事業名 | 障害児等の体験格差解消事業〈2019年通常枠〉 |
| 活動対象地域 | 静岡県西部地区 |
| 資金分配団体 | 公益財団法人 ブルーシー・アンド・グリーンランド財団(B&G財団) |
| 採択助成事業 | 障害児等の体験格差解消事業 草の根活動支援事業・全国ブロック〈2019年度通常枠〉 |
【この記事の事業に関連する「優先的に解決すべき社会課題」】
1.子ども及び若者の支援に係る活動
(1)経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援
(2)日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援2.日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援(5)日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援
【この記事の事業に関連する「持続可能な開発目標(SDGs)」】
| 目標4【教育】 | 目標10【不平等】 | 目標11【持続可能な都市】 | 目標14【海洋資源】 |
|
|
|
|