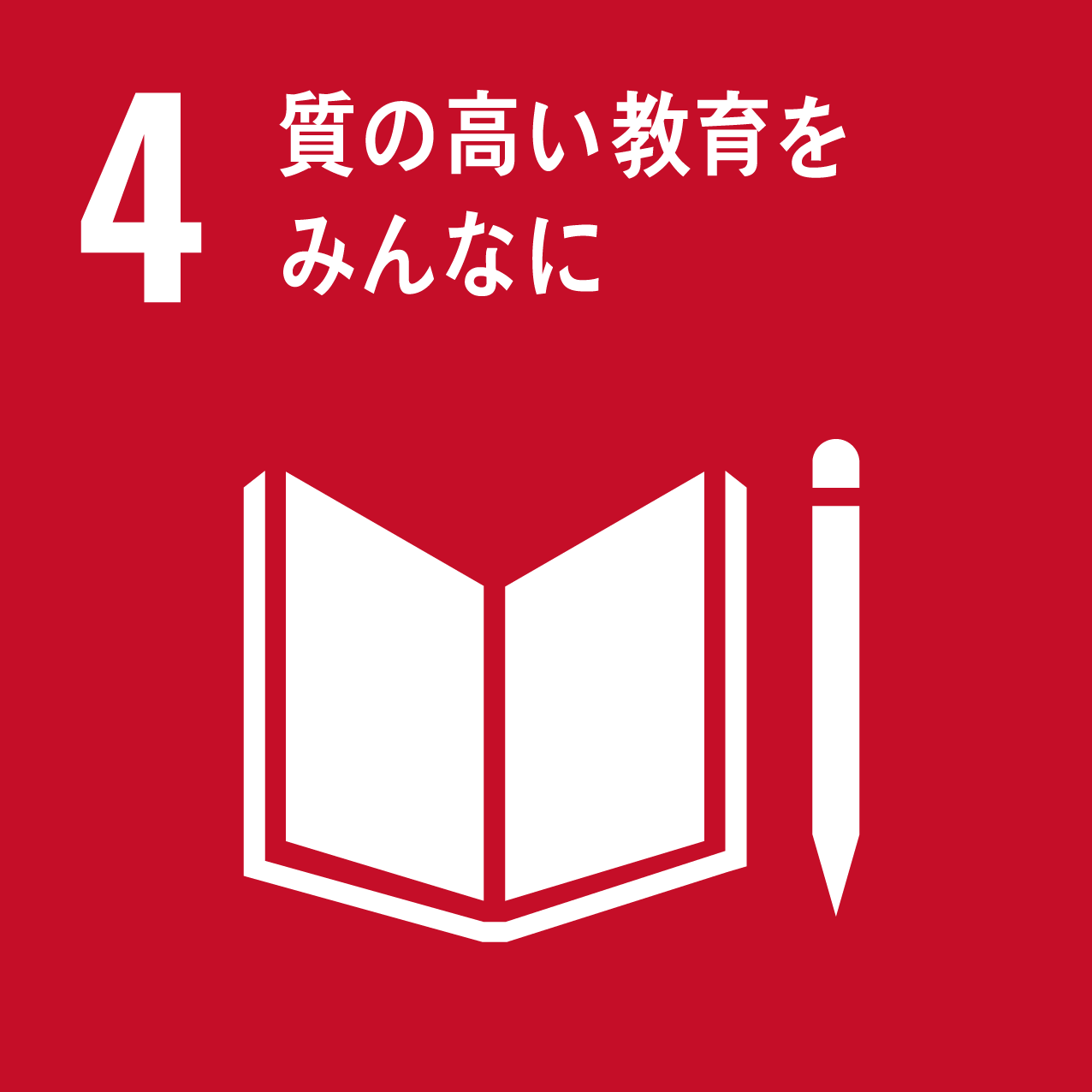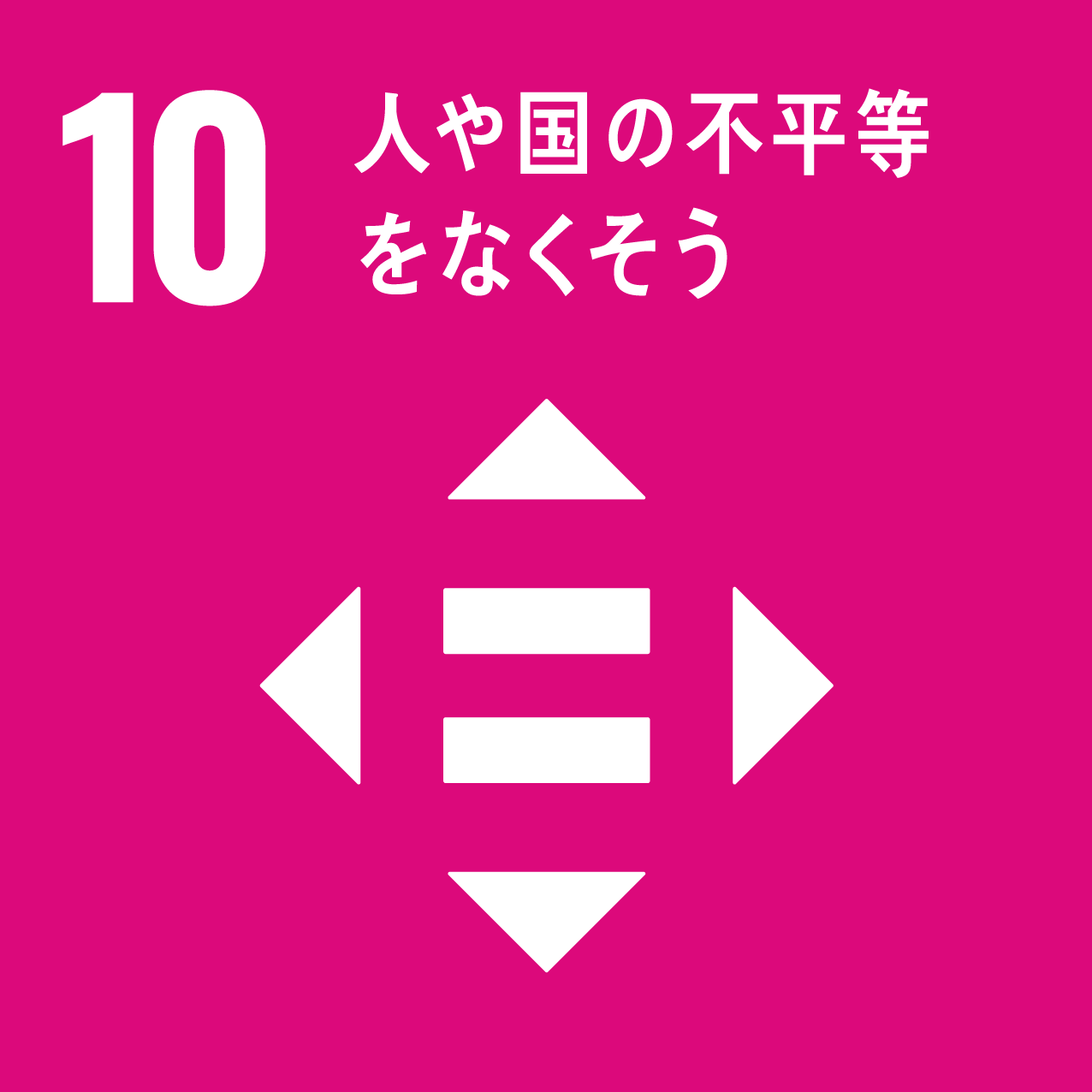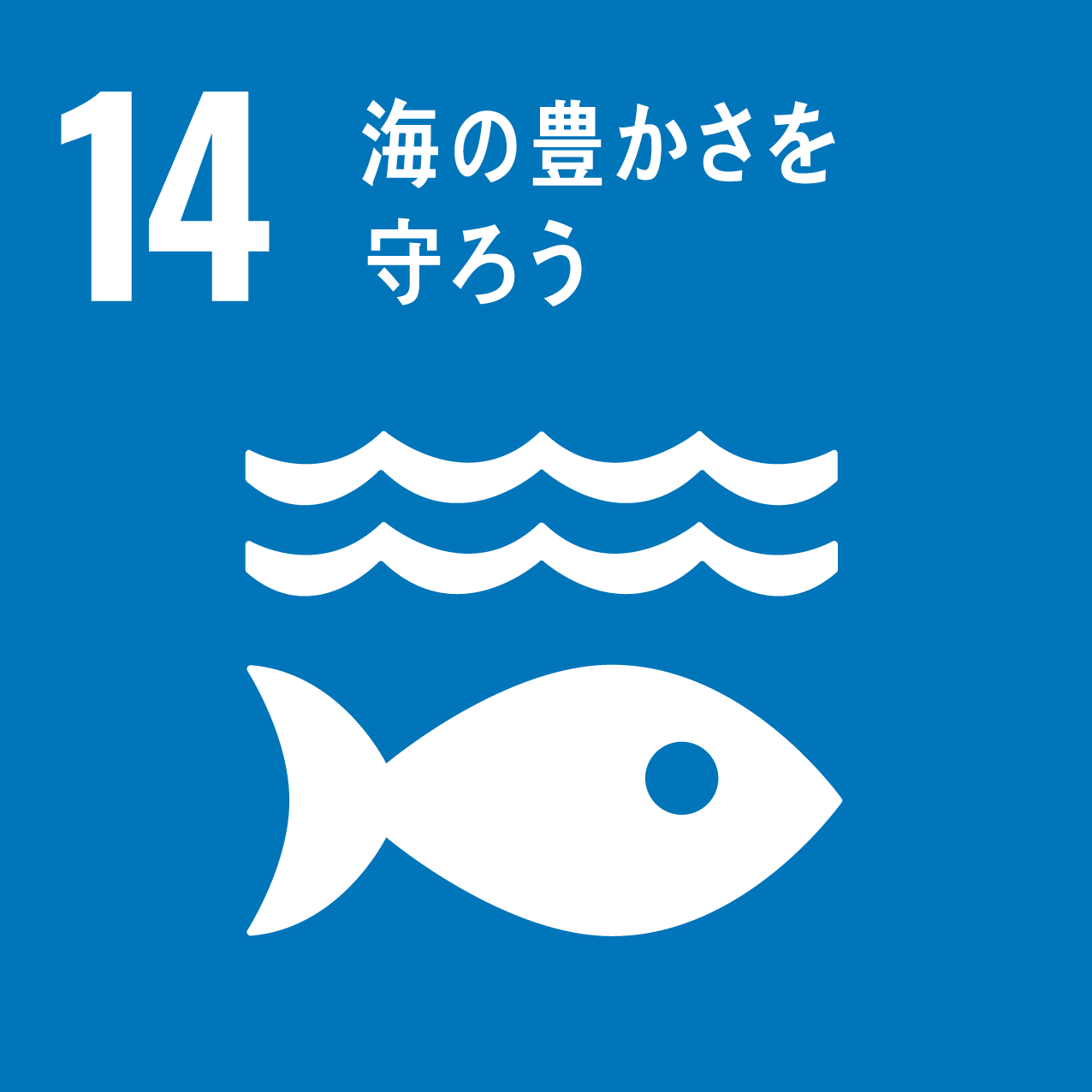非行少年が社会復帰をしようとしても、様々な理由で再び犯罪に手を染めてしまう例は少なくはありません。2019年度通常枠〈資金分配団体:更生保護法人 日本更生保護協会〉の実行団体として、少年院出院後に地元を離れてやり直したいと考える少年・少女の社会復帰と社会自立の支援をしているのが、『全国再非行防止ネットワーク協議会』です。今回は、全国再非行防止ネットワーク協議会代表・高坂朝人さんに、非行少年を取り巻く状況や彼らへのサポートの現状、そして休眠預金活用によって実現した活動内容や思いを、評論家でラジオパーソナリティーでもある荻上チキさんが伺いました。その様子をレポートします。
▼インタビューは、動画と記事でご覧いただけます▼
社会復帰の選択肢を広げる。県域を超えた非行少年へのサポート
荻上チキさん(以下、荻上):「全国再非行防止ネットワーク協議会(以下、全再協)」は、どのような活動をされているのでしょうか?
高坂朝人さん(以下、高坂):主な活動は2つです。
一つは罪を犯した少年・少女が地元以外の県外で生き直したいといったときに、民間団体同士で連携し、県域を超えてのサポートをすることです。
もう一つは、少年院に入っている少年・少女が社会復帰をする際の引き受け先を探すことです。
受け入れてくれる人が誰も見つからない場合、収容期間を過ぎても半年、また1年と延長されてしまうという現状があります。そうした状況をゼロにしたいと思い、活動しています。

荻上:非行に走ってしまった少年・少女たちが地元を離れて県外で暮らしたいと思うのには、どのような背景があるのでしょうか。
高坂:自分が生まれ育った地域で複数人で犯罪を繰り返していると、やり直したいと思っても非行仲間や怖い先輩に「また一緒に悪いことをしよう」と誘われ、なかなか自分一人では断りきれずに犯罪を繰り返してしまうということがあります。そのような背景から、一旦、人間関係を整理して地元以外の場所でやり直したいと希望する子たちがいます。
荻上:法務省が作成する犯罪白書(※1)の統計でもっとも多く見られる再犯や再非行の理由が、「かつての仲間と繋がった」となっています。そうした少年・少女たちの再非行防止について対応しているわけですね。全再協は「ネットワーク協議会」とのことですが、どのような団体がこうした活動をしているのでしょうか。
※1:法務省・法務総合研究所が、犯罪防止、また犯罪者の改善や更生を目的として、犯罪の動向と犯罪者処遇などについて、統計資料を基に説明をする白書。
高坂:僕たち全再協は、非行少年のサポートが源流である広島の「食べて語ろう会」、大阪の「チェンジングライフ」、そして僕が理事長を務める愛知の「再非行防止サポートセンター愛知」の3つの団体で構成されています。実は全再協設立前からそれぞれ関わりがあって、例えば、広島の少年院を出院した少年が地元に戻るのは心配だということで、愛知で受け入れてサポートをしたり、逆に愛知から広島や大阪で受け入れてもらったこともあります。
荻上:県域を越えて民間団体同士で繋がっていくことで、より広く活動ができるようになったのですね。
高坂:そうですね。本気でやり直したいと思っている少年・少女が生き直すための選択肢が増えてきたと感じています。
少年・少女が非行に走った背景には、色々な要因が絡み合っています。犯罪白書の統計によると、少年院に入っている子では男子は3人に1人、女子は2人に1人が虐待経験を持っています。また家族との交流が困難だったり、家族関係が良好でも一人親家庭の上、家族自身もサポートを要していたり…。こうした場合、自分たちだけで解決しようとするよりも第三者の支えや理解が必要です。
実体験が活動の原動力に。苦しさを知っているからこそのアドバイス
荻上:高坂さんは、どうしてこういった活動を始められたのでしょうか?
高坂:大変情けないことなのですが、自分自身が非行少年であり、犯罪者でした。
僕は広島県広島市で生まれ育って中学1年生から非行に走り、少年院には2度入院しました。その後、24歳の時に現在の妻が妊娠がわかり、父親になることを機に、本気でやり直そうと決意しました。これは全再協を設立したきっかけにも通じますが、僕が更生しようと思ったとき、僕の周囲には暴力団関係者や犯罪歴のある人しかいなくなっており、その中でこれまでの仲間と縁を切ったり、誘いを断り続ける自信はありませんでした。そこで人間関係を整理するためにも知り合いのいない愛知県に妻と子どもと一緒に引っ越しました。
しかし、これまで全然関係がなかった愛知での仕事探しは本当に大変でした。中卒で職歴もありませんでしたし、また職に就いても続かないという状態で…。何か困った時に誰かに頼ろうとしても頼れる人もおらず、使える制度なども知りませんでした。また仮に助けてくれる制度や団体があっても、その当時は変なプライドが邪魔をして誰かに頼ることに抵抗を持っていて、頼れない自分がいたんです。
そうした経験から、自分の生活が少しずつ落ち着いてきたときに、今、過去の自分のように非行に走っている少年たちに「自分のような思いはして欲しくない」と思うようになりました。
悪いことを止めるならば、1日でも早くやめて生き直した方が絶対にいい。更生させるというよりは、一緒に食事をしたり、色々な話をしながら、少年たちが前に進むためのサポートをする活動を始めました。

荻上:支援する側、される側といった関係性だと相談しにくいところもありますが、少年院に入院している時からつながることができた知人や既に更生した先輩といった関係性ならば、さまざまな制度や次のステップへのアドバイスも聞きやすくなりそうですね。
高坂:僕自身もそうでしたが、非行に走っていた当時は、「罪を犯している先輩や友だちは仲間で信頼できる人」、「犯罪をしたことがない人は別世界の人」といった具合に区別してしまっていました。一生懸命関わってくれていた人の話にも聞く耳を持てず、素直な気持ちにもなれませんでした。だからこそ、こうした支援をする大人たちを信頼できないという少年たちの気持ちにも寄り添いたいと思っています。
アンケートにより見えてきた、連携を求める事業者の声。
荻上:今回実施している休眠預金を活用した事業について、その取り組みなどを教えてください。
高坂:現在、3団体でネットワークを作っていますが、やはり、もっと色々な民間団体が手を取り合って連携していくことで、罪を犯した少年・少女たちや成人の人たちにとって、より立ち直りやすい環境や選択肢が拡がると思うんです。
僕たち3団体も運営する「自立準備ホーム※2」という制度が施行されて2021年で丸10年。2021年4月1日時点では全国445の事業者が登録しています。年間約1,500人が利用していますが、事業者同士の横の繋がりはなく、全国組織もない状況です。ホームがある場所や事業者などは公表されていないため、それぞれの事業者が孤軍奮闘しながら活動してきました。
そこで、法務省保護局と全国の保護観察所に協力をしてもらい、全国の自立準備ホームの実態調査(アンケート)を実施しました。その結果、事業者同士の連携や全国組織ができたら、ぜひ参加したいという声が100団体ほどあることがわかりました。しかし、それらを実現するためには各地から携わるメンバーを集めて会議をしたり、色んな人からの協力や理解を得るためのシンポジウムを開催したり、さまざまな面で資金が必要になります。そこで、休眠預金活用事業に申請し、採択していただきました。
※2:法務省の「緊急的住居確保・自立支援対策」に基づき、刑務所や少年院を出所後に一時的に住むことができる民間施設。事前に保護観察所に登録されたNPO法人や社会福祉法人などが、社会復帰を目指して各自の自立をサポートします。
荻上:この間、色々と活動されている進捗状況はいかがですか?
高坂:そうですね。これまで自立準備ホームの横の繋がりはもちろん、ホームの運営者による勉強会すらありませんでした。そこで、中部、近畿、中国、3つの地方で自立準備ホーム事業者が集まる勉強会を開きました。全国を8つの地域に区切っており、まだ実施していない地域でも勉強会を行っていきます。
加えて、令和4年3月21日に国立オリンピック記念青少年センター(東京)で自立準備ホーム事業者の全国組織の発足を行い、設立シンポジウムを開催する予定にしています。その準備を進めるにあたって、法務省保護局や更生保護を支える団体の方々に日頃の活動報告やご協力のお願いを継続して行っていくことや、全国組織の情報を発信していくためのウェブサイトの準備なども休眠預金を活用して行っています。
休眠預金活用事業によって生まれた新しい繋がりが、事業継続の力に。

荻上:実施された勉強会ではどのような話し合いが持たれているのでしょうか。
高坂:一度の勉強会に約30〜40人が参加しています。勉強会の中では例えば、罪を犯した人の中には、知的障がいや精神障がいのある人とか、その他の病気を患っている人もいて、そうした人たちへの医療や福祉面での対応の難しさについてですとか、入所者によってホームの部屋が壊されてしまったときに、現在はそうした損害を各ホームが持ち出しで対応しているケースが多いためにそのような対応の大変さについて話されていまし
また、自立準備ホームの運営はどこも資金面での厳しさがあり、正社員を雇用することはどこのホームもほぼ難しい状況です。そのため有償ボランティアのような形でやっている事業者がほとんどであるため、「スタッフを探したり育成すること」や「事業を継続していくこと」の難しさについての話が多く出ました。その他、情報交換を行っていくなかで、医療や福祉で困った際に頼れる制度を知らずに、仕事ができない入所者が払うことができない医療費をホームが持ち出しで負担している例があることわかり、「そんなやり方があるんだ」と事業者にとって発見があったりもしました。
とにかくこれまで横の繋がりがなかったので「自分たちだけがこんなに大変だ」と思っていたのですが、勉強会を実施することでどの自立準備ホームも同じような課題を抱えている仲間であることが分かり、「自分たちと一緒だ」と知ることで元気になり、改めて「これからも継続していこう!」と各事業者が互いに勇気づけ合う会となりました。
荻上:勉強会は支える側のノウハウを共有することはもちろん、支える側が心が折れそうなときにさらに支えあうというような側面もあるのですね。
個別の団体で活動するより複数の団体が連携することの強みはどういった点にお感じになりますか?
高坂:「自立準備ホーム」は保護観察所に登録をして、委託を受けて対象者と関わっていきますが、その過程で「制度事業とはいえ、ここは変えられないのか」と悩ましく思うこともあります。そのようなとき1団体では声を上げるのにも限界がありますが、複数の団体が繋ってネットワークとなることによって法務省所管の保護局や関係各所と意見交換ができています。他にも、自立準備ホームの制度ができて10年目で初めて「運営資金が少しでも充実するように」と概算要求という機会をいただけたり、連携することで少しずつ光が当てていただけていると感じています。
荻上:休眠預金という資金があることで繋がりを強化することができ、その繋がりによって交渉窓口として機能するようになって行政との対話も進んでいるのですね。それで、予算が付けばさらに事業が拡がっていくというわけですね。最後に、休眠預金活用制度への参画を検討されている方々へメッセージをお願いいたします。
高坂:僕自身の経験から、「非行を行なった少年・少女」や「罪を犯した成人」には1日でも早く非行や犯罪を止めて欲しいと心底願っています。
被害者の方、その周囲の方、家族も不幸になる。そして、当事者である本人も一人では止めづらく苦しい。色々な人の支えを受けて更生を目指せれば…と思いますが、その罪を犯した人に対する制度やシステムは、まだまだ他の社会課題と比べると少なく、民間団体が取り組もうと思っても資金を得られる仕組みがほとんどない状況です。今回の休眠預金を活用した助成を受けることができて助かっていますし、本当に必要だと思う活動を継続できることに大きな希望を感じています。

(取材日:2021年10月28日)
■高坂朝人さん プロフィール■
全国再非行防止ネットワーク協議会代表のほか、NPO法人再非行防止サポートセンター愛知で理事長を務める。「世界中の再非行を減らし、笑顔を増やすこと」をテーマに鑑別所や少年院で過ごす青少年のサポートや、各種メディア出演や講演会などを積極的に行う。実体験によるアドバイスが多くの少年・少女、また同志の心を掴み、近年では行政との連携も果たし、全国的なサポートの実現に向け尽力している。
■荻上チキさん プロフィール■
メディア論をはじめ、政治経済やサブカルチャーまで幅広い分野で活躍する評論家。自ら執筆もこなす編集者として、またラジオパーソナリティーとしても人気を集める。その傍ら、NPO法人ストップいじめ!ナビの代表理事を務め、子どもの生命や人権を守るべく、「いじめ」関連の問題解決に向けて、ウェブサイトなどを活用した情報発信や啓蒙活動を行なっている。
■事業基礎情報
| 実行団体 | 全国再非行防止ネットワーク協議会 |
| 事業名 | 罪を犯した青少年の社会的居場所全国連携 拡充事業 |
| 活動対象地域 | 全国 |
| 資金分配団体 | 更生保護法人 日本更生保護協会 |
| 採択助成事業 | 安全・安心な地域社会づくり支援事業〈2019年通常枠〉 〈2019年度通常枠・草の根活動支援事業・全国ブロック〉 |
今回の活動スナップは、浦和レッドダイヤモンズ株式会社(資金分配団体:一般社団法人RCF)が11月20日に実施した〈このゆびとまれっず!ハートフルケア〉イベントにJANPIAスタッフが参加した際の様子をお伝えします。
活動の概要
浦和レッドダイヤモンズ株式会社は、一般社団法人RCF(20年度緊急支援枠資金分配団体)の実行団体として、「スポーツクラブによる困窮世帯支援事業」に取り組んでいます。
「このゆびとまれっず」は、地域の課題解決を目指し、クラブがきっかけとなって(=浦和レッズが指を掲げて)、支援者・賛同者とともに(=仲間を募って)、継続・拡大していくことを目的とし、
休眠預金活用事業をきっかけに立ち上がったアクションプログラムです。
さいたま市内の子ども食堂を利用している子どもたちへの支援策として、
心と体をケアするスポーツプログラム「ハートフルケア」、
食料・飲料・文具などの物的支援を行う「REDS Santa」、
本活動を広く発信することで支援の輪を広げる「このゆびとまれっず!特設サイト」の
3つの柱で構成されています。
活動スナップ
2021年11月20日、〈このゆびとまれっず!ハートフルケア〉が実施されました。
当日はさいたま市の子ども食堂を利用している親子69組146名が参加しました。




※アンプティサッカーとは 主に上肢、下肢の切断障害を持った選手がプレーするサッカー。義足・義手を外し、日常の生活やリハビリ医療目的で使用しているクラッチ(杖)で体を支えて競技を行います。 |



| 実行団体 | 浦和レッドダイヤモンズ株式会社 |
| 事業名 | このゆびとまれっず! |
| 活動対象地域 | 埼玉県 |
| 資金分配団体 | 一般社団法人RCF |
| 採択助成事業 | スポーツクラブによる困窮世帯支援事業〈2020年度緊急支援枠〉 |
2021年10月初旬、佐賀県と長崎県で外国人を支援する実行団体4団体と資金分配団体(佐賀未来創造基金・未来基金ながさき)がオンライン上で集まり、約2時間にわたって成果報告会を実施しました。その様子を、前半・後半の2回に分けて紹介します。今回は「前半・プレゼン編」です!
コロナ禍における外国人分野の支援を実現
日本に住む外国人の方々は、生活に関わる情報を母国語で得ることが難しいという課題があります。ある在留外国人向けに実施された調査では、在留外国人の9割が「日本語がわからないことで困った経験がある」と回答しています※。特に、新型コロナウイルス感染症や自然災害など非常事態に見舞われると、言語の壁はさらに大きな問題になります。非常事態における「母国語での情報」や「日本語学習の支援」がどれだけ心強い支えになるのかは想像に難くありません。
2020年度新型コロナウイルス対応支援助成の資金分配団体である公益財団法人 佐賀未来創造基金(コンソーシアム構成団体:一般財団法人未来基金ながさき)は、コロナ禍における外国人分野の支援を実現するため、4つの実行団体を選定し活動しています。今回の成果報告会は、その4実行団体と資金分配団体がオンライン上で集い、「新型コロナウイルス対応緊急支援助成での取り組みと成果」を共有し、その成果を発信することを目的に開催されました。会では、実行団体4団体がそれぞれの休眠預金活用事業での取り組み内容についてプレゼンを行いました。以下、それぞれの団体のプレゼンの概要をご紹介します。
※在留外国人総合調査「日本語学習について」株式会社サーベイリサーチセンター(2020年9月23日)
佐賀県国際交流協会(SPIRA)「外国人住民に対する多言語情報提供事業」

1990年に設立されたSPIRAは、「国の国境をなくそう!」(Free Your Heart of Borders!)をスローガンとして活動しています。佐賀県に住んでいる外国人は7,031人(2020年1月1日時点)で、うち40%が技能実習生。国籍はベトナムが一番多く、次いで中国、フィリピン、韓国、朝鮮、インドネシアの順になっています。
SPIRAが「外国人住民に対する多言語情報提供事業」に取り組んだ背景には、日本語が苦手な外国人住民は日本での生活が困難な状況にあり、さらに新型コロナウイルス感染症の情報へリーチできずに深刻さを増しているという課題がありました。そこで、新型コロナウイルス感染症に関する様々な情報や手続きなどについて、母語による情報提供や相談対応ができる環境を整備することにしました。具体的には、協会職員等で対応可能な英語・中国語・韓国語・やさしい日本語に加えて、ベトナム語・インドネシア語・タガログ語・ネパール語ができる人を採用して週1回勤務してもらい、多言語による情報提供と国際交流プラザでの対応を目標としました。
事業の成果として、まずはSNS等による情報の随時発信があります。
「佐賀県から出ないようにというメッセージが出ても、外国人の方に届かなければ出かけてしまい、外国人への偏見につながりかねない。できるだけ早く伝える必要があり、随時発信してきました」と矢富さん。

Facebookの発信には絵をつけて、一目で内容が分かるように工夫しています。ホームページでも多言語で情報を提供し、ワクチン接種の流れを紹介したり、YouTubeの説明動画に10言語の字幕をつけたりしています。また、市から要請を受けて、集団接種の会場で受付から接種完了まで外国人をサポートしました。そのほか、2021年8月に佐賀で豪雨災害が起こった際には、8言語で情報を提供しました。
「多言語パートナーと県職員などで力を合わせて取り組んでいます。みんなが暮らしやすい佐賀になるように今後も続けていきます」と意気込みを語りました。
ユニバーサル⼈材開発研究所「平時から備える災害時多言語発信~母語グループ設立による包括的外国人支援~」

サワディー佐賀はタイ人のネットワークを作るため、2018年にスタートした団体です。タイ料理教室や東京五輪のホストタウンとしてのおもてなし、祐徳稲荷神社への通訳ボランティアの派遣などを行い、災害時はタイ語での発信にも力を入れていました。それらの活動が評価されて、2020年度「ふるさとづくり大賞」で団体表彰(総務大臣表彰)を受賞しました。

佐賀県では災害が起こると佐賀県災害時多言語支援センターが立ち上がり、8言語で対応されます。サワディー佐賀では、行政でカバーできていない残り4%のミャンマー語・タイ語・シンハラ語に対応すべく、事業に申請しました。そして、タイをモデルケースとして、ミャンマーとスリランカのFacebookのページを作りました。今年2月にミャンマーでクーデターが起こった際は、ミャンマー人を対象としてオンラインの生活相談会も行いました。
サワディー佐賀では、通常LINEグループ(62人登録)でやり取りをしています。災害など外国人に知らせたい情報が発生した場合は、山路さんがやさしい日本語に変換し、翻訳チームがタイ語に翻訳し、タイ人メンバーがネイティブチェックをしてから発信するようにしています。ミャンマー語とシンハラ語も同様の仕組みにしました。2021年8月豪雨の際は、タイ語・ミャンマー語・シンハラ語で情報発信を行いました。
「平時からグループを組織化していたことで、スムーズな情報発信ができた。平時こそ、こういう体制を作っておくことが重要だと改めて実感しました」と山路さんは力を込めます。
山路さんは、NPOが災害情報を発信するメリットは多いと指摘します。まず、行政は公平性を担保するために同時発信に配慮するが、NPOは翻訳が完了した言語からスピーディに発信できること。翻訳のソースとして、行政の情報だけでなく新聞やテレビ、気象庁など多岐にわたる情報を扱えること。
また、「翻訳スタッフに謝金を支払えることも大きい。ボランティアでお願いしているといずれ息切れしてしまう」と山路さん。さらに、グループ化によって顔が見えているため、必要とされる情報だけ翻訳すればいいという状況ができました。
今後は、少数言語による情報を県単位ではなく広域で共有できるプラットフォームを作りたいと考えています。同事業は地球市民の会で継承し、佐賀県の企業版ふるさと納税を一つの財源とし、地域おこし協力隊をスタッフとして続けていくそうです。
Treasures of The Planet「長崎発信型在住外国人支援プロジェクト」

「長崎発信型在住外国人支援プロジェクト」では、長崎市在住の外国人を対象としてオンライン・アンケートや面接インタビューを行い、新型コロナウイルス感染症の広がりによって直面している問題を把握。多言語対応のポータルサイト(UNIVERSALAID.JP)を制作して、その結果を公開するとともに、新型コロナに関する医療や福祉情報をはじめ、長崎在住の外国人が必要としている情報を掲載して運営・管理するという事業を実施しています。プロジェクトは長崎大学の多国籍な先生や学生たちの協力のもとで進めています。
まずは学生たちとアンケートの質問事項を検討の上、12か国語に翻訳。アンケートを依頼するチラシとアンケート用のサイトを作り、約360人から回答を得ることができました。その結果を集計して、英語のレポートと、要点を11か国語に翻訳したレポートをUNIVERSALAID.JPのサイトにアップしました。また、アンケートの回答などをもとに、長崎在住の外国人が求めている情報をリストアップして、それらが掲載されているウェブサイトをピックアップ。WHO、厚生労働省、みんなの外国人ネットワーク、長崎県国際交流協会、長崎県や長崎市の国際関係や生活支援の部署などに連絡を取り、コンテンツの共有とリンク、多言語翻訳、サイトへの掲載許可をもらい、UNIVERSALAID.JPで公開しています。なお、翻訳は長崎大学の留学生グループなどにチェックしてもらっています。

サイトについてプレスリリースを出したところ、西日本新聞と長崎新聞、インドネシアのサイトで紹介されました。Googleアナリティクスによると、現在のユーザーは約490人で、リピーターが約2割になっています。
松尾さんは「外国人の方々に話を聞いてみると、すでにあった外国人向けの情報サイトと比べて、UNIVERSALAID.JPは非常に分かりやすくて使いやすいと評価いただいています。今後は、新型コロナ感染症の情報だけでなく災害情報やゴミの出し方などいろいろな記事を掲載して、サイトを見てくれる人やリピーターを増やしていきたい」と総括しました。
フリースクールクレイン・ハーバー「在留外国人親子の日本語習得&不登校支援」

フリースクールクレイン・ハーバーは長崎で、不登校の子どもたちの支援を17年にわたり行ってきました。「外国人の親を持つ子どもが、日本の学校に行きづらさを感じて不登校になるケースも見てきました」と高村さん。また、同団体では、使わなくなった学生服とランドセルを生活困窮家庭やひとり親家庭に寄付する活動をしており、外国人の子どもに寄付することもありました。
そんな中、新型コロナウイルス感染症の影響で仕事を失ったり就業が困難になったりしている外国人親子を支援しようと、日本語専門学校のあさひ日本語学校と連携して事業に取り組むことにしました。事業の概要は、長崎県内在住の外国人を対象に、就労を目的とした日本語教育をオンラインで無料で行うというもので、必要に応じて子どもにも支援を行います。オンライン授業のため、離島を含めて広い範囲の外国人を支援することが可能です。県内の9市町村の役所や社会福祉業議会などにチラシを配って周知を図り、長崎新聞にも記事が掲載されました。その結果、現在4人にオンラインで授業を行っており、うち1人は実際に仕事に就くことができました。

課題としては、目標の10人になかなか届かないことが挙げられ、「問い合わせをいただいても、対面での授業がいい、夜間に授業してほしい、就業は望んでいないなどと条件が合わなかったケースもあります」とのこと。また、今のところ受講者に子どもがいないため、子どもとつながって支援した事例がないことも課題であり、「これまでとは違う子ども関係の部署や教育委員会に周知するなど、アプローチの方法を工夫していきたい」と高村さん。「コロナ禍でマイノリティの方々にしわ寄せがきている。そのような方に優しい長崎でありたいと思っています。次年度以降については、コロナの状況をみながら、どうやってニーズに対応していくかを考えて、もっと多くの外国人親子に関わっていきたい」と今後に向けての意気込みも話しました。
| 資金分配団体 | 公益財団法人佐賀未来創造基金 (コンソーシアム構成団体:一般財団法人未来基金ながさき) |
| 事業名 | 新型コロナ禍における地域包摂型社会の構築 ~地域で暮らす全ての人の安心と未来をつなぐ~ |
| 対象地域 | 佐賀県、長崎県 |
| 実行団体 | ★公益財団法人佐賀県国際交流協会(SPIRA) ★一般社団法人ユニバーサル人材開発研究所 ★NPO法人Treasures of The Planet ★特定非営利活動法人フリースクールクレイン・ハーバー ・九州ケータリング協会 ・佐賀県地域共生ステーション連絡会 ・NPO法人ナガサキリハビリテーションネットワーク ・一般社団法人すまいサポートさが ★:今回の記事で紹介されている団体 |
https://youtu.be/WS89S3IVjuI
https://youtu.be/FyeSC12K8lA
「ダブルハルカヌーって安全性が高いんですよ」。そう爽やかな笑顔で話してくださったのは、有限会社SHIPMANの代表取締役を務める城田守さん。2019年度通常枠〈資金分配団体:公益財団法人 ブルーシー・アンド・グリーンランド財団〉の実行団体として、活動拠点である静岡県立三ヶ日青年の家(以下、青年の家)を舞台に浜名湖畔で体験格差をなくすべく、水辺の活動やさまざまな支援に取り組んでいます。今回は、日本でここにしかない「ダブルハルカヌー」に特別支援学校の子どもたちが挑戦!その体験学習の様子、そして休眠預金を活用したSHIPMANの取り組みなどを取材しました。
ダブルハルカヌーに挑戦。美しい浜名湖をみんなで駆け抜けよう
11月初旬、浜松市内の特別支援学校の生徒たちが三ヶ日青年の家を訪れていました。集まっていたのは、小学4年生と5年生の男女8名。聴覚障害を持つ児童たちです。彼らが今日体験するのは「ダブルハルカヌー」。浜名湖畔で、日頃、触れ合う機会のない水辺での体験学習に挑みます。

体育着姿の子どもたちが集まったのは、マリーナ広場にある艇庫(ボート倉庫)。その一角で、まずは水辺での活動の際に注意すべきことや漕ぎ方などについて学びます。大きなポイントは3つ。1つ目はSHIPMANの指導員や先生たちの話をよく聞くこと。2つ目はできる限り大きな声を出す。そして3つ目は素早い行動を心掛けること。水上ではちょっとした甘えが事故に繋がるため、一緒に乗船する艇長の指示に従って行動しなくてはなりません。続いて、水辺の活動では着用が欠かせないライフジャケットについて指導を受けます。
「ライフジャケットは必ず体が浮くようにできています。もし水の中に落ちてしまったら、体育座りのようにできるだけ小さな姿勢を保って救助を待ちます。落ち着いて襟元をしっかり掴んで下にぐっと引っ張りながら上を向いて呼吸を確保してください。暴れたり、泳いだりすると体力を消耗するので、静かに救助を待つよう注意しましょう」

着用したライフジャケットを触ってみたり、友だちと話してみたり、緊張した表情を浮かべつつも、どこか楽しげな様子の子どもたち。次は艇長の指導でパドルの持ち方や漕ぎ方を学びます。元気な挨拶が艇庫いっぱいに広がると、木製パドルが順番に配られました。いろいろ試してみたいところですが、ここはぐっと我慢!
「今、みんなに配ったのが、カヌーを漕ぐときに使用するパドルです。大事な道具なので杖にしたり、振り回したりしてパドルを傷つけたり、周りのお友だちに怪我をさせないように注意しましょう!」
艇長の両脇で引率の先生が手話で説明をします。口の動きと手話で持ち方を学ぶと、子どもたちは素早く行動。ダブルハルカヌーは二層のカヌーが並行に繋がれた仕様のため、乗船する場所によってパドルの持ち方が異なります。向かって右側の列は左手で上部の三角部分を握り、右手で一番細い部分を持ちます。左側の列は、その逆です。しっかり持つことができたら、いよいよ漕ぎ方の練習。友だちにぶつからないように距離を保ちます。
「漕ぐ時は “1、2、ソーレ!” という掛け声に合わせてパドルを動かします。艇長が1、2、みんなはソーレ!です。パドルを戻す時は後ろの人に水がかからないように、水からスッと抜くようなイメージ。ちょっとみんなで練習してみましょう!」

少し照れくさそうにしていた子もいつの間にかどんどん大きな声に。テンポ良くパドルを動かしながらイメージを膨らませます。しっかり準備ができたら、ここで持参した小さなタッパーに補聴器や人工内耳をしまいます。子どもたちは水辺での活動やプール学習の際はもちろん、雨の日も傘がない時は必ず装具を外すといいます。聞こえにくく不安に感じる際は周囲の状況をよく見ることに意識を向けるなど、日頃の自立活動の時間を通じて学んでいます。

水上で学ぶ「思いやり」と「協力」の姿勢
艇長に続いて艇庫を出ると、雄大な浜名湖が子どもたちを待っていました。ヨットハーバーに到着すると休眠預金を活用して購入したという真新しい桟橋から、指示に従ってダブルハルカヌーに乗船していきます。
浜名湖は海とは異なり、時折、すれ違う漁船による引き波以外は、大きな波もなく水面は穏やか。これまでに経験のない揺れに驚いて声を出す子もいましたが、ぐんぐん進むうちにいつの間にか掛け声も大きく、パドルも力強く揃った動きに。前にいる仲間の動きをよく見て、後ろの友だちのことを思いやり、協力して漕いだダブルハルカヌー。ヨットハーバーに戻った時には、子どもたちの姿はちょっぴりたくましく見えました。


引率をした小学部学部主事・下村先生は言います。
「事前にパドルの使い方などの学習はしてきたとはいえ、本当に初めての挑戦でした。桟橋を渡る時も恐々とした様子でしたが、指導を受けながら『ああ、こうやって漕ぐんだ!』と理解する様子も見受けられ、本当によく漕ぎきったなという思いです。今後もぜひ参加させていただきたいと思います!」
非日常の体験を終え、どこか誇らしげな表情をした子どもたち。秋らしい柔らかな日差しを受けてキラキラと輝く湖面に負けない、格別な笑顔が印象的でした。後日、SHIPMANには子どもたちからの寄せ書きも届いたそうです。
水上で仲間を思いやり、共に協力をして行動をすることは、日常生活にも通じており、コミュニケーションを図る上でも役立つというSHIPMANの城田さん。改めて休眠預金を活用した取り組みや今後の活動などについて伺いました。
風から、そして波から学ぶ。非日常の体験を子どもたちに届けたい!
「この青年の家は社会教育施設として、“来て!見て!やって!感動を!!”をテーマに昭和36年に発足しました。浜松は工場の町。当時の若い工員さんたちによる青年団が交流の場として活用していたんです。指定管理者として運営に携わったのは約8年前(2013年)。私たちが得意とする海洋活動を中心に、年齢、性別、そして国籍を問わず、誰でも利用できるイベントや体験学習を始めたんです」

城田さんは前職であるヤマハ発動機時代に培った経験を活かし、2003年にSHIPMANを立ち上げると同時に「浜名湖海の駅連絡会」で救助艇の手配などのボランティア活動にも従事してきました。浜名湖は浜松市と湖西市に跨る汽水湖(区分は二級河川)。水難事故などが起こった際に管轄である県警よりも素早く最寄りのマリーナから救助に行けるよう取り組んでいたそうです。しかし2010年に悲劇が起こります。一人の少女が湖畔での体験学習の際に亡くなってしまったのです。
「安易な任命が最悪の事故に繋がります。だからこそ、『How to=方法や手順』だけではなく、常に『Why=なぜ?』を基本に、会話をしながら活動することが重要です。そうした点を踏まえて、私たちSHIPMANのスタッフは知識や技術を伝えるインストラクターを超えた、活動の価値や意味をも伝えていくインタープリターとして取り組むことにしています。指定管理業務は水辺に関するプロでなければできません」

事故は絶対に起こしてはいけない。悲しく、また悔しい思いをしたからこそ、強い意志と使命感を持って、安全で安心な水辺の活動を目指す城田さん。スタッフと共にさまざまな訓練の日々を送り、再び浜名湖畔で体験学習が行えるようになりました。
小さなことから一歩ずつ取り組む。地域との連携で実現する支援活動
「休眠預金活用事業に手を挙げたのは、水辺の活動を通じて非日常的な体験を子どもたちにしてもらいたいと思ったことがきっかけです。特に、家族と十分なコミュニケーションを図ることが難しい子やさまざまな事情から殻に閉じこもっている子、あるいは障害を持つ子たちのために何かできないかとずっと考えてきました。子どもたちが気軽に訪れてSUPを楽しんだり、釣りをしたり。まずは徒歩や自転車で来られる範囲に住んでいる課題を抱えた子どもたちから漏らさず受け入れて行こうと、地元の小中学校の先生方にも協力を仰いでいます」
そんな取り組みの中、コロナウイルス感染症の蔓延を受けて県内外から年間約3万8000人が訪れていた青年の家も利用者が激減。城田さんは登校することもできず、居場所を失ってしまった地域の子どもたちを青年の家で預かる決断をします。その活動は施設内での学習だけではなく、駅のペンキ塗りや児童公園の草刈りなど、多岐にわたりました。
「近隣地域だけでなく、少し離れた街からも子どもたちが来るんです。青年の家は開放さえしていれば、誰でも利用できますからね。延べ200人の子どもたちを相手に、海洋指導員や元教職員、現役の校長先生まで、多くの人たちの協力を得て活動をしていました」
まさに草の根的な取り組みを経て、城田さんは地域とも連携し、さまざまな課題をクリアしてきました。休眠預金を活用した日々の活動から感じた今後の目指すべき方向はどのようなものなのでしょうか。

体験格差のない社会を目指して漕ぎ進むSHIPMAN
「特別支援学校はもちろん、不登校の子どもたちにも焦点をあててた活動をしたいですね。既に4年ほど前から地元の教職員を集めて水辺での活動を中心にさまざまな研修を定期的に行なっています。休眠預金活用事業の中長期計画の一環として、現在の取り組みや活動を、地域と連携しながら社会に向けて周知させることを目指して活動しています」
学校という場所を離れても子どもたちがいつでも帰れる場所をつくるべく、日々奔走している城田さん。昨今、注目を集める総合的な学習への取り組みにもチャレンジし、指導する側の意識改革にも余念がありません。またこうした活動を通じて、年齢や性別関係なく学べる機会や場所を設け、単独では難しい事象も県域を超えて同じ思いを持つ同志と連携することで「取りこぼさない社会づくり」を実現したいと言います。
マリンスポーツをはじめとする海洋活動を武器に、水辺のインタープリターたちの飽くなき挑戦は続きます。
■資金分配団体POからのメッセージ
SHIPMANの強みは、やはり城田さんの海洋活動を通じた青少年育成にかける果てしない情熱です。休眠預金活用事業を遂行する上で立地、施設や設備を含め、青年の家は素晴らしい環境。自治体や地域との連携を築き、特別支援学校や訪れる各団体に安全かつ楽しめるという育成プログラムや次へ繋がる研修の実施が実現できているのは水辺のプロからこそ。「ダブルハルカヌー」を新たに制作することで「健常者と障害を持つ子どもたちの体験格差」という課題も乗り越え、格差解消を目指した取り組みは、まさに本事業の目的に沿った活動です。インクルーシブ社会である昨今、誰もが社会の一員として集える地域社会づくりに向け、城田さん率いるSHIPMANと共に歩み、課題に取り組んでいきたいと考えています。
(公益財団法人 ブルーシー・アンド・グリーンランド財団 / 遠藤卓男さん)
取材・執筆:天屋 詠
【事業基礎情報】
| 実行団体 | 有限会社SHIPMAN(静岡県浜松市) |
| 事業名 | 障害児等の体験格差解消事業〈2019年通常枠〉 |
| 活動対象地域 | 静岡県西部地区 |
| 資金分配団体 | 公益財団法人 ブルーシー・アンド・グリーンランド財団(B&G財団) |
| 採択助成事業 | 障害児等の体験格差解消事業 草の根活動支援事業・全国ブロック〈2019年度通常枠〉 |
【この記事の事業に関連する「優先的に解決すべき社会課題」】
1.子ども及び若者の支援に係る活動
(1)経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援
(2)日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援2.日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援(5)日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援
【この記事の事業に関連する「持続可能な開発目標(SDGs)」】
| 目標4【教育】 | 目標10【不平等】 | 目標11【持続可能な都市】 | 目標14【海洋資源】 |
|
|
|
|
休眠預金活用事業の成果物として資金分配団体や実行団体で作成された報告書等をご紹介する「成果物レポート」。今回は、資金分配団体『公益財団法人ちばのWA地域づくり基金〈2020年度緊急支援枠〉』が事業完了にあたって作成した冊子『「地域連携型アフターコロナ事業構築」事業報告書』をご紹介します。
休眠預金等活用新型コロナウイルス対応緊急支援助成「地域連携型アフターコロナ事業構築」事業報告書
ちばのWA地域づくり基金は2012年に市民からの寄付により設立した市民コミュニティ財団です。休眠預金等活用法における新型コロナウイルス対応緊急支援助成「資金分配団体」に選定されました。新型コロナウイルス感染症の蔓延防止対策や経済活動の停滞により経済的、精神的、身体的影響を受けた社会的孤立リスクの高い層のニーズに対応する支援活動に対し、さまざまな要因による格差が拡大しないよう、また当事者を支える支援事業が消滅または後退することによって二次的被害が生じることのないよう、アフターコロナを見据えた当事者へのアプローチと、よりインパクトの高い支援事業構築のための事業開発・実施と事業推進のための環境整備、人材育成等の基盤づくりへ公募助成を実施しました。
この度事業報告書を作成しましたので、ぜひご覧ください。
【事業基礎情報】
| 資金分配団 | 公益財団法人ちばのWA地域づくり基金 |
| 事業名 | 地域連携型アフターコロナ事業構築事業〈2020年度緊急支援枠〉 |
| 活動対象地域 | 千葉県 |
| 実行団体 | ・特定非営利活動法人ダイバーシティ工房 ・特定非営利法人ケアラーネットみちくさ ・特定非営利活動法人 生活困窮・ホームレス自立支援 ガンバの会 ・特定非営利活動法人子どもの環境を守る会 J ワールド ・特定非営利活動法人ワーカズコレクティブういず ・労働者協同組合ワーカーズコープちば |
コロナ禍の外出自粛により、女性に対するドメスティック・バイオレンスをはじめ、性暴力被害などの被害の深刻化が懸念されています。こうした被害に対する日本の法制度は、諸外国に比べて大幅に遅れている状況です。加えて、支援側の活動資金、専門知識を持つ人材不足が大きな課題となっています。今回は、資金分配団体「特定非営利活動法人 まちぽっと(2019年度通常枠)」の実行団体として活動する『特定非営利活動法人 全国女性シェルターネット』の北仲千里さんに、ジャーナリストの浜田敬子さんがDV被害者への支援活動や現状、そして休眠預金を活用した今後の展望をインタビューした様子をお届けします。”
▼インタビューは、動画と記事でご覧いただけます▼
DV被害者支援の世界へ。直面する活動継続の難しさ
浜田 敬子さん(以下、浜田):全国女性シェルターネットは、1998年(平成10年)に活動を始められたそうですね。
北仲 千里さん(以下、北仲):女性に対するドメスティック・バイオレンス(以下、DV)や虐待被害といった問題が、世界的に大きく注目を集めたのが1990年代後半。95年に開催された「第4回世界女性会議(北京女性会議)」をきっかけに世界各国でこの問題に対するシェルター運動が活発になり、日本でも各地で手づくりのDVシェルターを始める方が増えていきました。97年には現団体の前身となる「女性への暴力駆け込みシェルターネットワーキング」がシェルターを運営する人の情報交換を目的として活動をスタート。翌年には各関係者が北海道札幌市に集まり、第一回のシェルターシンポジウムを開催しました。

浜田:北仲さんはいつ頃から、全国女性シェルターネットの活動に入られたのでしょうか。
北仲:2000年か、もう少し後からの参加です。90年代半ば頃は、大学院生として、ジェンダーに関する問題をテーマに研究をしていました。そんな時、私たちの周囲で偶然にもセクシャルハラスメント(以下、セクハラ)に関する問題が浮上し、大学キャンパスでこれらに対する運動を始めたのです。
そこで大学におけるセクハラについての情報を発信するホームページを制作したところ、日本中から相談などが殺到。その後、少し上の世代の専門家の方々から性暴力やDV被害者の支援をするNPOを立ち上げるから一緒にやらないかと声を掛けられ、DVシェルターにも関わりだしたのがきっかけとなりました。
浜田:北京女性会議をきっかけとして、日本でも草の根的にシェルターが増え始めたとのことでしたが、そういった団体のネットワーク組織として「全国女性シェルターネット」があるのですね。
北仲:はい。正確な数は分かりませんが、全国に100か所以上のシェルターがあると言われています。その中で、私たち「全国女性シェルターネット」に加盟している団体は現在60団体。90年代に活動をはじめた方々に団塊の世代が多いこともあり、最近は減少傾向という現状です。
浜田:必要とされているのに、活動の継続が難しいということでしょうか?
北仲:海外では、90年代に支援をはじめた志がありノウハウも備えている民間団体に、国や自治体が事業を委託するという形の支援がスタンダードです。一方日本は2001年に“公的な相談センター”という形で支援がスタートしたので、民間と国や自治体との連携が生まれにくく、我々は勝手に支援をしているという状態です。活動をしている人たちには人件費はほとんど払われておらず、施設の家賃などをなんとか寄付や助成金でまかない、この数十年やってきました。そのような活動の継続にはやはり限界があり、ひとつ、またひとつと閉鎖しています。しかし、新しく団体を作りたいというグループからの問い合わせもそれなりにくるので、DVや虐待被害に対する関心は高まっていると感じていますが、自分たちで資金を生み出せる活動では決してないので、そうした面でも継続していくのは難しく、苦しいですね。
閉ざされた世界からステップアップできるまで。DV被害者を取り巻く現状
浜田:支援活動をはじめて約20年間、DVや性暴力を巡る状況の変化について、北仲さんは今、どのようにご覧になっていますか?
北仲:「セクハラ」もそうですが、「DV」という名称がつくまでの方が恐らく酷かったと思います。
浜田:そうした事象がたくさんあっても、皆さん声をあげなかったわけですね。

北仲:把握もできていなかったと思います。例えば、90年代や2000年代くらいに役所や自治体が市民を対象に行ったある調査では、人生経験豊富な60代以上の女性は、DVに関する問いにだけ「無回答」する確率が高かった。声に出してはいけない風潮があったということだと思います。恐らくセクハラなども昔の職場の方がずっと酷かった。その一方で、若者たちはこうした問題に関心があって「これは怒っていいんだ」という認識があり、きちんと回答していました。とても興味深い結果でした。
それから10年が経過し、私がいくつか見た調査結果では60代の方々が無回答になっていることは少ないよう感じています。つまり、女性たちはDVなどに対して怒ってもいいと感じ、声をあげやすい環境になってきていると言えます。
とはいえ、アジア圏のDVシェルター関係者と情報交換をしたり、各国の統計などを調査・比較したりすると、香港やシンガポール、台湾などに比べて日本の被害率が高いように感じます。それは圧倒的な法制度の遅れが原因。海外では、大学で福祉などを学んだ若者が性暴力や性虐待、DVや児童虐待を救うソーシャルワーカーを目指し、公的な施設はもちろん、民間団体は人気の就職先となっていて、きちんと職業として成り立っています。自分たちで資金を調達する私たちとはまるで異なる状況です。
<参照>
国際ジェンダー学会ウェブサイト
http://www.isgsjapan.org/journal/files/15_kitanaka_chisato.pdf
徹底的に向きあって寄り添う。国境を越えて共通する大事にしていること

浜田:こうした支援には段階があると思いますが、全国女性シェルターネットが日常の支援活動の中で大事にしているポイント、そして財政的な問題も踏まえて、困難だなと感じている点を教えてください。
北仲:世界中の関係者と話すと、実は大事にしていることが一緒だということが分かります。
DV被害者の方々は「お前なんかどうしようもない奴だ」といった具合に、相手にコントロールされてしまっていて、「ここから逃げられない」とパワーが落ちてしまっている状況です。そこで、私たちはその状態の方たちとなんとか繋がりを持ち、とにかく話を聞き、自分は本当に何がしたかったのか、どんな気持ちだったのか、自分自身で決めてもらうように促します。「あなたはこうすべきだ」などというと、再び誰かに支配されてしまうので、なりたかった自分を決めるのにじっくり付き合うというのが、民間でも公的なセンターでもすごく大事で一番難しいことなんです。
自身が元被害者という支援者も非常に多く、自らの経験から被害者の恐怖心や辛かった出来事を理解できます。被害者本人が今じゃないところに進むことを考え、決めてもらう。そして、その気持ちを整理し、作戦を一緒に立て、作戦を実行するためには「逃げてくる部屋があるよ」「シェルターもあるよ」など、こまごまとしたお手伝いをする。「世の中にはなかなか伝わらなくても、私たちには分かるよ」と時間をかけてじっくり話しをしています。
もう一つ、私たち民間支援者が大事にしているのは「同行支援」です。なぜなら、まだまだ社会的にはこうした問題に対する理解が低い状況だからです。解決に向けて、「警察に行ったらいいよ」「弁護士に行ったらいいよ」と、ただ対処法を助言するだけの中途半端な寄り添い方をすると、行った先で分かってもらえるとは限らないので、また傷ついてしまう。そこで私たちも一緒に行くことで、例えば警察で聞かれることを学んだり、時には「いやいや、そうではないですよ」と説明したりします。理解のある弁護士さん、不動産屋さん、本当によく協力してくれる病院など、社会の様々な方たちとの繋がっていくためには、やはり被害者の方と一緒に行動することがとても大事です。それによって社会の壁も見えるし、道も拓けてくると思います。
浜田: 新型コロナウイルス感染症のパンデミックによってこれまでとは暮らし方が異なり、家にいる時間が長くなる、失業したストレスなどによるDVや性暴力の被害が世界中で増えたと言われています。その状況は日本でも深刻でしたか?
北仲: そうですね。新型コロナ関連の給付金が国民に配られるという話を聞き、かなりの関係者が「震災の時と同じことが起きる」と考えたんです。世の中が非常時となり一気に何かが動くときに、DVで家を出ているというような特殊な事情を持った人たちは、置き去りにされていってしまう可能性があると感じたのです。
10万円の給付金が配られましたが、それが世帯主に配られるということでしたから、一番欲しい被害者(母子)が受け取れないのではないかと考えました。また外出自粛などを受け、相談に来ていた人はこれなくなる。加えて女性の雇用もかなり厳しくなり、家を出ようとしていた人も出られなくなる。そうした懸念から、国に要望書を提出しました。
浜田:普段、行政から見えない、もしくは、見えづらい課題を抱える方たちは、何かがあったときに一番先に救わなければならない方たちだ思いますが、救えていないということでしょうか。
北仲:そうですね。外国人の方もそうだと思います。情報も届きにくく、そのような方たちにはオーダーメイド的な配慮をしなければいけないのですが、できていないと感じています。さらには、支援したいと考えても、資金面と人材の確保が大きなハードルとなっています。
休眠預金を活用して学びの場を。慢性的な課題を今、乗り越える
浜田:休眠預金活用事業ですすめておられる活動の一つに専門の相談支援員の育成がありますが、どのような育成研修となっていますか?
北仲:日本では、こうした相談支援が専門的な仕事だと思われていません。外国ではソーシャルワーカーやDVアドボケット(被害者の声を代弁して支援する人)と呼ばれているのですが、日本の相談員はただ悩みを聞くだけの誰でもできる仕事だと考えられているのです。しかし実際の被害者支援は、心理系の知識はもとより、行政の制度、法的な知識など様々なことを知っていないとできません。相談員は「誰でもできる仕事」ではなく、専門的な知識が必要な職業なのです。
近年、DVの相談窓口があることが大事だと、各県に「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」が設置されました。このような窓口をもっと増やしていくという時に、誰でもいいからと相談員を集めると、とんでもないことになります。知識のない人に相談した人は、本当に気の毒です。
官民ともにそろそろ世代交代というのもあるので、若い世代で相談員になりたい、支援をしたいと思っている人たちがちゃんと知識を習得して、OJTでトレーニングを受けられる育成の場をつくる必要があると考えています。とはいえ、国に要望しているだけでは実現は遠い。何を学ぶ必要があり、どんな知識が必要か、どんな人が相談員になるべきなのかを一番知っているのは、私たち民間の支援者です。世界の支援者ともつながっているので、世界的な基準の情報を得ることができます。だからこそ、私たちがまず「これが専門職」と定義し、人材を育てられるテキストやカリキュラムをつくることが急務だと思っています。
休眠預金を活用して3年間の事業を実施しています。1年目は、どんなカリキュラムにするかをとことん検討したり、海外の情報を収集したりしました。2年目となる今年は、最終的なカリキュラムを詰めています。コロナ禍でオンライン化が急速に進み、e-ラーニングについても学び、全国の希望者が自分のペースで学べるようなオンライン学習システムづくりにも取り組んでいます。今年の冬には試験的な運用を始め、来年には受講者を募集する予定です。その後は、新たに立ち上げた一般社団法人で資格認定を行う仕組みを計画しています。

DV被害・性暴力に関する認定資格で、専門家を育成。より手厚い支援を目指す
浜田:e-ラーニングを受けて認定資格を得た人が、どんな形で活動することを思い描いていますか?
例えば、専業でなければいけないのか、副業として自分ができる範囲でも活動できるのか。学んだ方がたくさん育ってきたときの将来像をお聞かせください。
北仲:民間もそうですし公的にもDVや性暴力の相談施設を増やそうとしているので、相談員を育て増やしたい。だからこそ、相談員をやりたいと考えている方々にまず学習してもらい、同じレベルで支援活動に取り組める人たちを育て、最終的にはきちんとした職業として確立したいというのが一つの想いです。
もう一つは、講座にいくつかのコースや段階を設定していくことを計画しています。役所の方、裁判所の職員、警察関係者など、すでにDVや性暴力の被害者と向き合う仕事をしている方もいますし、これから新たに関わる人もいます。また、NPOやボランティアで関わりたい人もいます。入門コースからより専門的トレーニングを受けられるコースなど、受講内容を検討しています。そうして「私も専門家だ!」と自信を持って言える人材を育てたいですね。
浜田:役所の方や警察関係者が受講できるというのはすごく大事ですね。先ほどのお話のように、被害者が二次的に傷ついたり、また傷つくのが嫌だから相談に行かないという方もいらっしゃるので、最初の段階できちんとした対応ができれば、相談しやすくなりますよね。加えて、ボランティア活動などで関わりたいけれども何ができるのか、どう関わればよいかわからない方もいらっしゃると思います。そのような方のためのコースもあるとのことで、視野が広がりやすく、支援者を増やすことにも繋がりそうですね。
北仲:そうですね。実はDVだけではなくて、性暴力の相談を受けられる人が少ない。私は、セクハラに関する仕事に長く携わっていますが、セクハラへの正しい対応を判断できる仕組みを持っている組織も本当に少ない。二次被害、三次被害の嵐なんです。被害者が相談窓口を訪れたり、会社に訴えたり、行動を起こした後で「何でそんな対応をしたの?」というような事例が多く、結局、窓口ができても本当の支援まで辿り着けません。
今回の取り組みを通じて、各組織や役所や警察の対応の仕方など、社会全体をもう少しグレードアップすることにつながればと考えています。
浜田:そういう意味で相談員、そして支援員の育成・養成事業というのはすごく意味があり、価値がありますね。休眠預金を活用してみていかがですか?
北仲:自治体がNPOや民間シェルターに対して多少は支援してくださるんですが、事務所・シェルターの家賃補助などを対象に年間で数十万円ほど。基盤となる人件費や光熱費などは支援の対象外です。
「民間にまったく支援がいかないのは問題」ということで、内閣府がパイロット事業をやってくださっていますが、それは通常の事業に加えて新しく先進的な試みをしたところに対しての助成となっています。普通の活動が回せるような強い団体でなければ、助成対象になりにくい点が難しいところです。
実行団体として2019年度にまちぽっとの事業に採択いただき研修制度の立ち上げに取り組んでいますが、2020年度には新型コロナウイルス対応緊急支援助成の2019年度採択団体向けの追加助成も活用させていただきました。全国の関係者にこの8、9月、どんな支援活動をどのくらいの時間したのか活動報告をしてもらい、各自が働いた分の人件費を、緊急支援助成を活用して支払いました。現場の人からは「(この活動で)初めて給料をもらった」という声も多く届きました。
また、活動報告からは、何月何日に被害者Aさんの病院や裁判所に付き添った、今後への作戦会議をした、シェルターに入ってくる人の荷物運びを手伝ったなど、支援活動の実態がよく見えました。これまでは、なかなか支援活動の全容をつかむことができていなかったので、私たち民間シェルターの支援活動、イコール、被害者支援とはこういう活動なのだ、ということを描き、多くの方に伝えていくことにも活用させていただこうと思っています。そういう意味でも今回の助成はとてもありがたかったです。
浜田:助成をきっかけに活動が見える化したわけですね。今後の活動の発展が期待されます。今日はお話を伺い、本当に勉強になりました。ありがとうございました。
北仲:ありがとうございました。
■北仲千里さん プロフィール■
NPO法人 全国女性シェルターネット共同代表を務める傍ら、広島大学ハラスメント相談室准教授としても活躍中。1967 年和歌山県新宮市に生まれ、ジェンダー論を中心に社会学を専門に研究。名古屋大学大学院文学研究科博士後期課程修了後、1997 年頃より「キャンパス・ セクシュアル・ハラスメント全国ネットワーク」設立にかかわる。以後、DVや性暴力などに関する被害者支援にも積極的に携わる。
■浜田敬子さん プロフィール■
フリージャーナリスト。1989年に朝日新聞社に入社。「週刊朝日」「AERA」編集部を経て、2014年に「AERA」初の女性編集長に就任。2017年同社退社後はオンライン経済メディア「Business Insider Japan」日本版統括編集長を2020年12月まで務める。各種メディアにコメンテーターとして出演する傍ら、講演活動や執筆も行う。1996年山口県生まれ、上智大学法学部国際関係法学科卒業。
■事業基礎情報
| 実行団体 | 特定非営利活動法人 全国女性シェルターネット |
| 事業名 | 「女性に対する暴力」専門相談支援者育成事業 |
| 活動対象地域 | 全国 |
| 資金分配団体 | 特定非営利活動法人 まちぽっと |
| 採択助成事業 | 市民社会強化活動支援事業 〈2019年度通常枠・草の根活動支援事業・全国ブロック〉 |